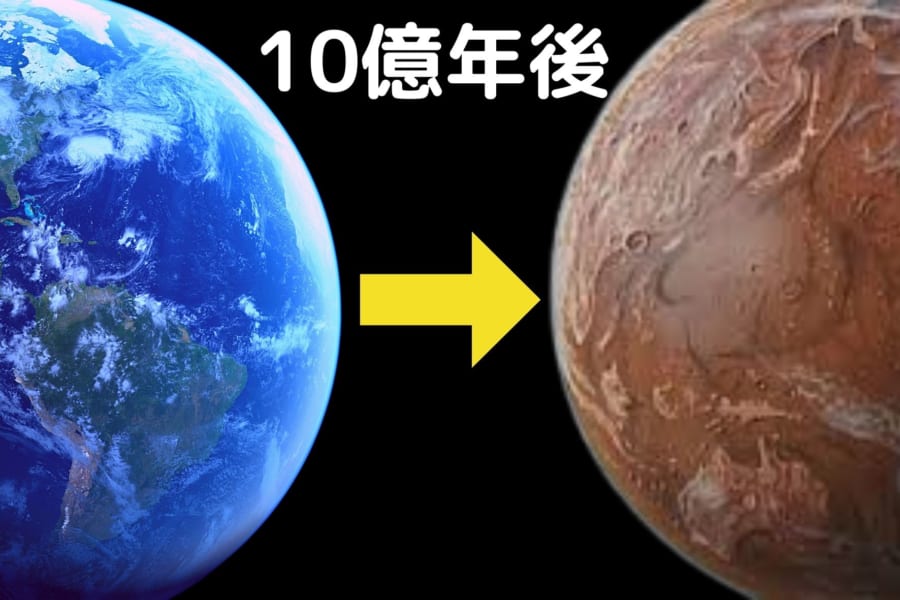なぜ史上最少に?北極の氷が溶けると何が起こる?
今回の記録的な海氷減少の要因として挙げられるのは、2024年12月から2025年2月にかけて北極圏周辺で続いた高温傾向です。
米国環境予測センター(NCEP)と米国国立大気研究センター(NCAR)が提供するデータによれば、この期間の気温は平年よりも明らかに高く、氷が形成されにくい状況が続いていました。
また、気温だけでなく、大気や海洋の循環変動、気圧配置の偏りなど複合的な要因が影響している可能性もあります。
特に、北極の気温上昇は他の地域の温暖化よりも速く進む「北極温暖化増幅(Arctic Amplification)」と呼ばれる現象が関係しているとみられています。
極地の氷が溶けてしまうと、太陽光を反射できる氷が消えて、暗い海面が露出してしまうことで、地球が太陽光をより吸収しやすくなり、温暖化に拍車がかかります。
加えて、氷が溶けることで海面上昇が起こり、沿岸都市の浸水リスクや島国の水没リスクが高まります。
さらには猛暑や寒波、台風やハリケーンの大型化などの異常気象を引き起こす危険性があるのです。

このような状況に対応するため、観測体制の強化が進められています。
JAXAは、2025年度に水循環変動観測衛星「しずく」の後継機となる人工衛星「GOSAT-GW」を打ち上げる予定です。
この衛星には、さらに高性能な「マイクロ波放射計3(AMSR3)」が搭載され、より精度の高い極域観測が可能になると期待されています。
かつては厚く広がっていた北極の氷が、わずか数十年で急速に縮小しているという現実は、私たちが思っている以上に深刻かもしれません。
遠く離れた北極で起きていることが、私たちの日常や未来にどう関わってくるのか。
その答えを知るためにも、こうした科学的観測とその継続的な発信が、ますます重要になっていくのです。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)