進化とは「捨てる選択」でもある
ここまで見てきたように、哺乳類が再生能力を失った背景には、がん、免疫、恒常性、環境といった複数の要因が絡み合った進化的判断があったと考えられるのです。
重要なのは、「再生能力=無条件で優れている」というわけではないことです。
進化とは、常に「ある能力を得るために、別の能力を捨てる」トレードオフの連続です。哺乳類は、再生という能力を抑える代わりに、高度な神経系、優れた免疫防御、複雑な行動様式を発達させることができたのです。
とはいえ、私たちの体にはいまだに、その「再生の設計図」が眠っています。近年の再生医療やゲノム編集技術の進歩により、こうした“封印された力”を再び目覚めさせようとする試みが進んでいます。
たとえば、視細胞を再生して視力を回復させたマウスの実験、皮膚や心筋の再構築、さらには人工的に「芽体(ブラステマ)」を生成して四肢や器官の再生を誘導しようとする研究も始まっています。
自然環境の中では、生き延びるために「素早く傷をふさぐ」戦略が有利でした。けれど現代の私たちは、医療という支えのもとで、安全に時間をかけて回復に専念することができます。
つまり、かつて進化が“捨てざるを得なかった”能力を、今の私たちは改めて取り戻せる環境にいるのです。
もちろん、そこには大きな壁もあります。がん化のリスク、免疫との干渉、そして生命操作にまつわる倫理的な課題――再生を再び可能にするには、これらすべてを慎重に乗り越える必要があります。
サンショウウオは腕を生成できるのに、なぜヒトにそれができないのか? その問いは「ヒトがどのような進化の道を選んだのか」という問題の答えでもあります。
哺乳類は、再生の力をあえて手放し、その代わりに「長寿」「知能」「社会性」といった複雑で洗練された生き方を獲得しました。
それでも、もし未来の医療がこの壁を乗り越え、再生の力を安全に呼び戻すことができたなら――それは単なる医学の進歩ではなく、私たちが一度手放した進化の“もう一つの選択肢”を、自らの手で再び選び取るという行為になるのかもしれません。




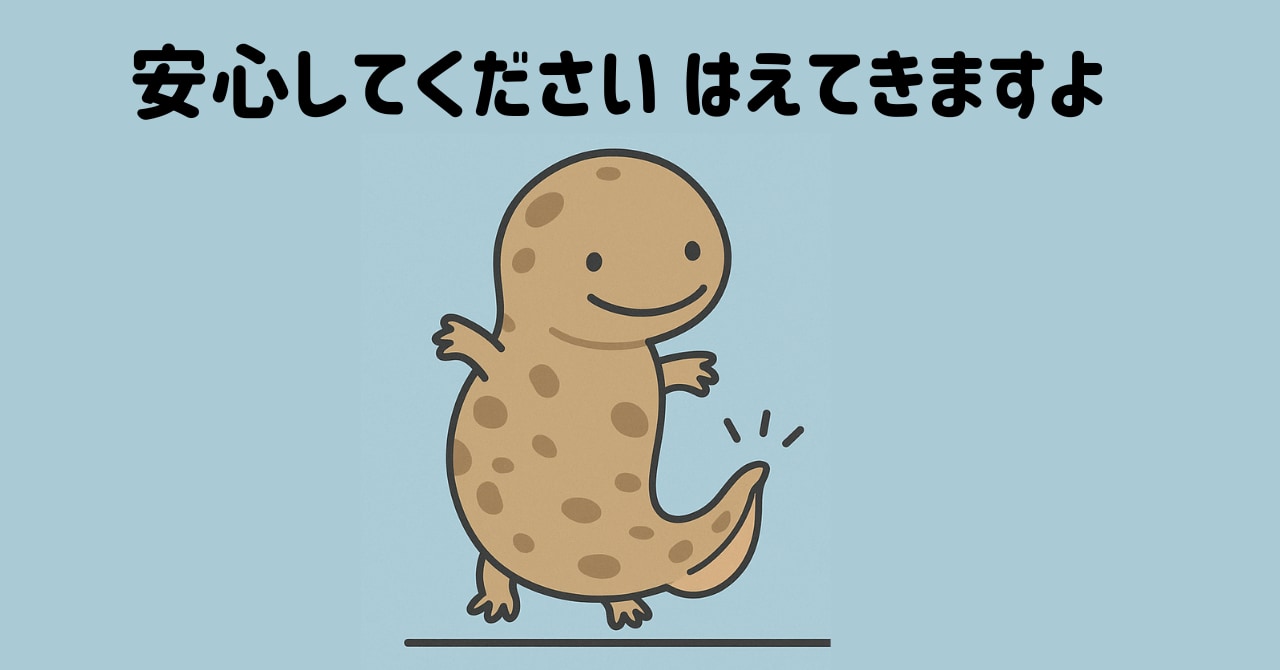



























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)





























とりあえず、「歯生え薬」の早期実用化に期待しましょうか。
理由が記載の4つだけなら、現代は野生動物や食糧調達、感染症等の危惧がほぼ無いし、再生能力あった方がいいな
むしろ突然変異とかでそういう人間出てきてもおかしくない