なぜ座りっぱなしは脳を萎縮させるのか?
では、なぜ「座る」ことが、脳の萎縮や認知機能低下につながるのでしょうか?
研究チームは複数の可能性を示しています。
まず1つ目は、血流の停滞です。
長時間動かずにいると、脳への血流が滞り、必要な酸素や栄養素が供給されにくくなります。
これは脳細胞の可塑性(新しい情報への適応能力)を低下させ、神経細胞の減少にもつながる可能性があります。
2つ目は、慢性的な炎症の誘発です。
座位行動の多い生活は、体全体に低レベルの炎症反応を起こしやすく、これが神経細胞の障害を進行させる要因になると考えられています。
3つ目は、シナプス形成の減少です。(シナプス=脳内の神経細胞同士がつながり、情報を伝達する接合部のこと)
動きが少ない生活では、脳内で情報を伝えるシナプスの形成が減り、記憶や学習機能が衰えていくのです。
動物実験でも、狭いケージで動きが制限されたラットは、走るホイールを使えたラットに比べて酸化ストレスの指標が高く、脳の状態が悪化していました。

さらに見逃せないのは、こうした悪影響が運動とは別のメカニズムで進行するという点です。
たとえ週に数回ジムに通っていても、日中ずっと椅子に座りっぱなしでは、脳へのダメージは避けられない可能性があるのです。
今回の研究は、「運動すればすべて解決」とするこれまでの健康常識に、一石を投じるものとなりました。
たとえ日常的にウォーキングをしていても、座っている時間が長ければ、脳は静かに衰えていく――そんな警告が、科学的データによって裏付けられたのです。
今この瞬間、あなたはどれだけの時間、座っているでしょうか?
脳を守る第一歩は「運動の時間を増やす」ことではなく、「座りっぱなしの時間を減らす」ことかもしれません。



















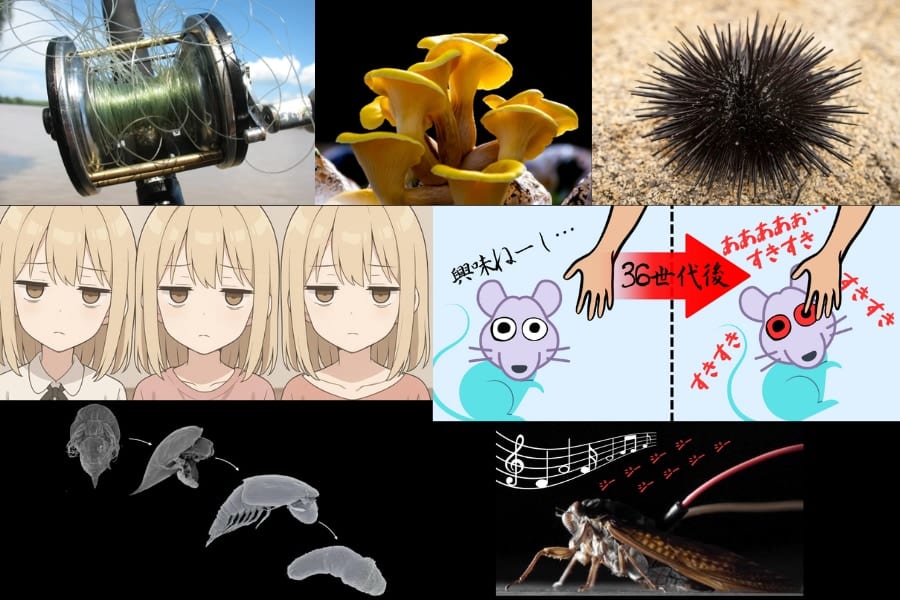








![[DABLOCKS] レザーケアセット 革靴 革ジャン 革製品 お手入れ](https://m.media-amazon.com/images/I/515FttM21TL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




























椅子座りでなく床座りの場合は、定期的に姿勢を変えやすく、脚裏の血管圧迫もし辛く、血流の面でマイナス効果が軽減されそうです。
つまり、デスクワークで脳萎縮や記憶力低下に自覚のある方は椅子座りから床座りへの変更で悪影響が軽減される可能性が考えられます。
詳しくは以下の記事が参考になります。
https://ayu-miyazawa.hatenablog.com/entry/2025/05/23/002351
学生の頃から病気で車椅子生活を余儀なくされた物理学者のスティーヴン・ホーキング氏は座りっぱなしですが、50年以上にわたり研究活動を続け、成果を挙げられたので、重要なのは座っている状態で脳をよく使用するか否かではないでしょうか。
学生の頃から病気で車椅子生活を余儀なくされた物理学者のスティーヴン・ホーキング氏は座りっぱなしですが、50年以上にわたり研究活動を続け、成果を挙げられたので、重要なのは座っている状態で脳をよく使用するか否かではないでしょうか。