成長すると逆に方言を使い始める人がいる
ここまでの話は、ASD児童は方言を使わない傾向があるというものでしたが、逆にある年齢を境に方言を使わなかったASDの人が、地元の方言を話すようになったという事例も確認されるようになりました。
そこで2019年に、弘前大学の松本敏治教授と菊地一文氏はこの問題について新たな研究を実施しています。
この研究では、8歳から23歳のASDと診断された5名を対象とし、それぞれが方言を使用し始めた年齢と、その前後に見られた対人スキルの発達状況を、55項目からなる質問票を用いて分析しました。
その結果、5名すべてにおいて、方言使用の開始とほぼ同時期に、意図理解・会話力・模倣・共同注意といった社会的認知スキルの発達が起きていたとわかったのです。
特に方言を使い始めた時期の前後で、これらのスキルが集中的に獲得・発達していたことが確認され、研究ではこの点を「方言の使用が、単に言語形式の問題ではなく、対人スキルの発達と深く関わっている可能性」を示す証拠としています。
また、当人たちに行った自由記述のアンケートでは、方言使用のきっかけとして、「クラスメイトとの関係の変化」「集団活動への参加」「信頼できる他者との関係の構築」など、当人が安心して他者と関わることができるようになった環境の変化が影響しているという報告が多く見られました。
つまり、ASDの子どもたちが方言を話し始めるには、対人スキルの発達と、それを促すような環境条件の両方が関わっていたのです。
こうした事例を見ていくと、私たちが普段は意識することのない、言語の意味や役割が見えてきます。
方言は単なる地域ごとの訛りや言い回しのクセだと認識している人は多いでしょう。
しかし、ASDの児童が、方言で話すことを避けるという現象や、信頼して話せる相手を見つけたり、対人スキルが向上すると方言を使うようになるといった現象は、方言の使用が単に知識や習慣の問題ではなく、社会性の発達や対人関係のあり方と結びついていることを示しています。
今回の研究はASDの人たちに関する報告ですが、コミュニケーションの問題で悩む人達は大勢います。
こうした事例の研究は、私たちが意識していないコミュニケーションの裏に潜む疑問を紐解くのに役立つのかもしれません。












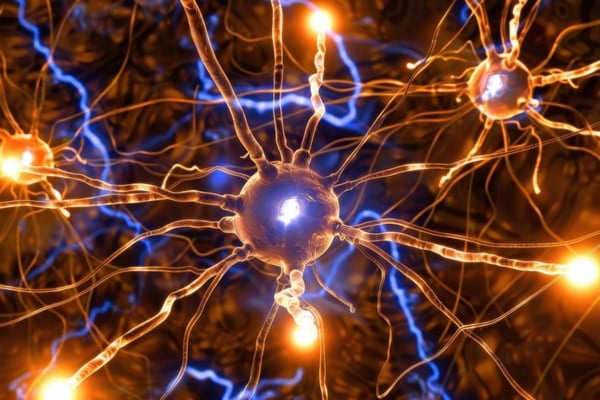















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)




























確かに、ASDの知人は方言を使いませんでした。
ASDは先天的にコミュニケーションが苦手なのではなく、信頼できる相手に恵まれなかったためコミュニケーションの機会があまり得られずASDと呼ばれる状態に陥っている、ということかもしれないですね
この研究の主役である松本敏治「自閉症は津軽弁を話さない」読んだけどやや冗長だしASD当人の気持ちをあんまり理解しようとしてない感じでした。俺は主に後天的自閉症で
1 親父がASDでその血を継いだのと、親父がASD故に共感力が低く人付き合いの価値を理解しなかったり人嫌いであったため俺は就学までの6年半を引きこもらされる。更に親父の性格の悪さも刷り込まれる。
2 小学校で社会デビューして、幼稚園保育園に行ってなかったから一人も友達いない、対人スキルゼロだから友達作れない、性格悪い、外でろくに遊んだ事もなかったから運動も苦手でいじめられっ子まっしぐら
3 クラスメートが嫌いだから真似したくない、同じ事したくない、可能な限り天邪鬼に皆と違う事をする。方言喋らないのもそれ。
ASDならば大概いじめられた経験があったり疎外感孤独感を強く持っているもので、承認不足になり構って欲しい話を聴いて欲しいという気持ちから奇怪な態度を通して自己アピールする心理もあります。勿論単純にIQが低くて自分が何を望んでるのかや何が足りないのかも考える発想が無い人もいるでしょう。「自閉症は」にはそういう心理的背景が全く考察されてないんです。よくそういう人が意思ゃになれてるなって思いましたよ。ただこの記事を見て本出版後にはそのほんもちゃんと考えてくれてるみたいでやや安心しました。
方言は特定集団の文化であり紐帯です。その集団の一員に加わりたければ進んでその文化に同化されに行くし、その集団が嫌いなら文化も拒否します。坊主憎けりゃ理論です。周囲に溶け込もうとしないとスケープゴートになって変人呼ばわりされる、本人はその集団が嫌いになってますます溶け込もうとしない、もっと虐められる悪循環。そんなのASDとか関係なく誰にでもある事なのにその本ではそこらへんの視点が全く触れられていなくて、何でもかんでも先天的発達障害のせいにするかのような話ばかりが延々続いていたのです。
なるほどぉ。
当事者の見解を踏まえないと上辺だけの分析になってしまうのですね。