“生きた個体”は見つかるのか?
マーシュ博士らは、オーストラリア研究評議会などの支援を受け、標本の年代測定と、この洞窟でなぜ生きた個体が見つからなかったのかという謎の解明に取り組んでいます。
洞窟に残されていた生物の年齢を測定し、「この生態系に何が起きたのか」を探ろうとしているのです。
実は、近くの別の洞窟では、生きた新種の大型クモも発見されており、洞窟内で現在も生き続けている種が存在することは確認されています。
このクモもまた、目がなく、淡い体色をしており、巨大な巣を岩の間に張って生息していました。
画像はこちらから。クモが苦手な方は閲覧をお控えください。

興味深いのは、これらのクモやスズメバチのような種は、たった1つの洞窟にしか生息していない可能性があるという点です。
これはちょっとした環境の変化や捕食者の侵入によって、簡単に絶滅してしまうことを意味します。
実際、チームが調査中に見つけたのは「スズメバチ」だけではありませんでした。
洞窟内には、大量のキツネの糞や、死んだキツネの個体も確認されました。
現在、キツネが洞窟生物を捕食している可能性についても調査が進められています。
さらに問題なのは、今回調査が行われた地域が「大規模な再生可能エネルギー開発」の計画地に含まれていることです。
調査が行われた洞窟も、今後の開発で破壊されるリスクに晒されています。
ナラボーの洞窟は、まだ誰にも知られていない“生物のタイムカプセル”です。
もし失われてしまえば、そこにしか存在しない生命も永遠に失われてしまうかもしれません。





























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
















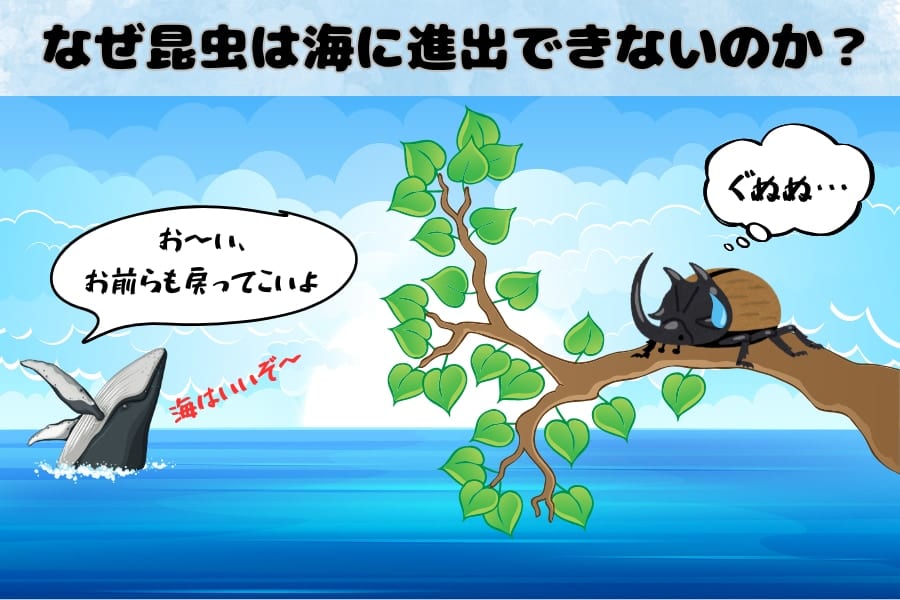


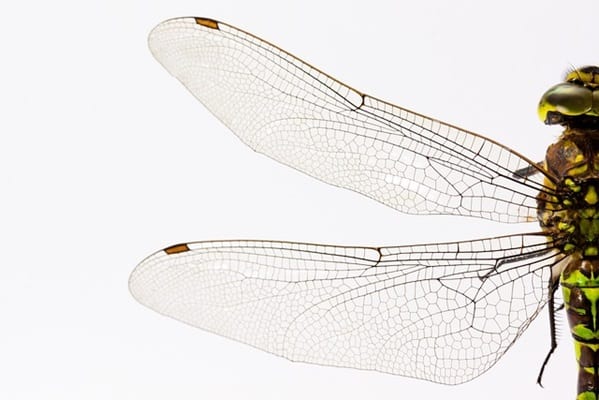
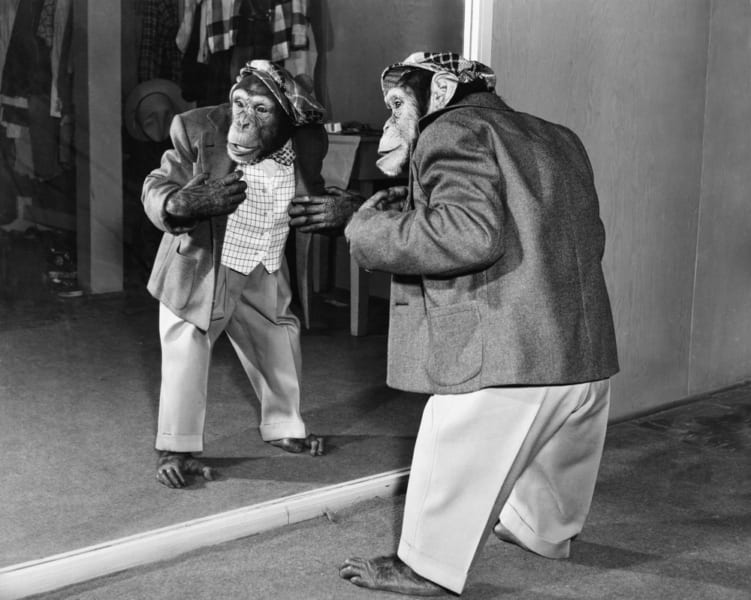







環境にやさしいという売りの再生可能エネルギーの開発で環境が壊されるという不思議な状況。
他の生物にとっての環境ではなく、人間の未来のための環境に優しいだから仕方ないですよね。それがむしろ自然の摂理とも言えるかと。
興味深い話でした。発見された「盲目のスズメバチ」の学名について、どこかで言及されてますか?
「スズメバチ」が英語の原文に出てくる「wasp」を訳したつもりなら、日本の読者に対して誤解を招きます。カリバチ(狩蜂)と訳すべきではないでしょうか。日本語でスズメバチとは、スズメバチ科でVespa属、Dolichovespula属またはVespula属のカリバチを指します。
まぁ「環境にやさしい=人間に都合がいい」ですからね。自然相手であれば、何もしない以上の優しさはありませんから。
>>自然相手であれば、何もしない以上の優しさはありませんから。
だいぶ思考停止してるね。
ハチからアリへの進化のヒントになるかも知れないね
いわゆるスズメバチ(Vespa等)ではないですね。誤解を招くので単純にカリバチやハチに訂正された方が良いです。
再生可能エネルギーという言葉が大嫌いです
再生不可能エネルギーというネーミングに改名したほうがいいのでは?
ソーラーパネルなどの設置によって破壊された自然が後に再生された事例はあるんでしょうか?
ソーラーパネルは本来であれば大地とそこに棲む生物達が享受する筈だった太陽光を横取りしてるだけってのも気に入らない
目に見えなくても必ず何かの弊害が起きているだろうとも
ちっぽけな虫ケラや洞窟なんて…
もっと大きな視点で地球のために再生可能エネルギーを増やそう
再エネ賦課金をもっと徴収して地球のためにがんばってる再エネ事業者を応援しよう
他の方も言及されていますが、
スズメバチではなくカリバチ、もしくはクモバチと表記するべきかと思います。
スズメバチとカリバチは分類的にイヌとネコくらい違うグループとなります。