性生活と脳の変化に意外なつながり
分析の結果、性生活の頻度が月に1回未満である人たちは、10年後における認知機能のスコアが有意に低下していることが明らかになりました。
この傾向は、年齢や性別、教育、所得、うつ症状、持病の有無など、認知機能に影響を及ぼすさまざまな要因を統計的に取り除いたうえでも、なお残るものでした。
認知機能の低下とは、たとえば言葉の出づらさ、記憶力の低下、注意が散漫になることなどにつながります。
そして、こうした変化は日々の生活の中でじわじわと感じられるものです。ちょっとした「ど忘れ」や、話している途中で言葉が詰まるような感覚――それが蓄積すると、やがては生活の質そのものに影響を及ぼします。
研究チームは、この結果を「セックスそのものが脳を直接活性化させている」というよりも、性的なつながりが、さまざまな健康的要因と連動している可能性を示すものと見ています。
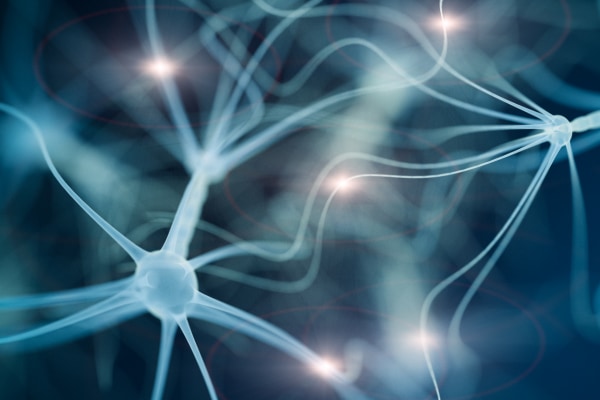
たとえば、性生活が活発な人は、パートナーとの良好な関係性を保っていたり、身体を動かす機会があったり、うつ傾向が少なかったりと、生活全体が活性化している傾向があると考えられ、これらの要因が複雑に影響し合っていると考えられます。
それが結果的に脳の活性化や健康に繋がっているというのは、不思議な話ではないでしょう。
とはいえ今回の研究は大規模データを用いた分析であり、あくまで「相関関係」を示したもので「因果関係」を直接証明したものではありません。
ただひとつ確かなのは、性生活が極端に減ることが、脳の健康にとって無関係とは言えないという事実です。
日本では、「セックスレス社会」という言葉がメディアでたびたび取り上げられますが、今回の研究が示したように、性生活の頻度が認知機能の低下と結びついているなら、これは個人の問題にとどまらず、社会全体の“脳の健やかさ”にも関わる問題になるかもしれません。
孤立が進み、ふれあいや会話が減っていく社会のなかで、私たちの脳は、機能が低下しやすい状況に置かれている可能性があるのです。
とはいえ、誰もが「セックスの頻度」を自由に選べる状況にあるわけではありません。現代はパートナーがいない人も多いとされていますし、性に積極的な気持ちになれない人も珍しくありません。
だからこそ、大切なのは「行為」ではなく「つながり」なのかもしれません。
今回の研究は、性行為に着目していますが、示している事実は人と心や身体を通じて触れ合い、“自分がここにいる”と感じられるような経験が、脳にとって大きな意味を持つということです。
たとえば、友人との何気ないおしゃべりや、ペットと触れ合う時間。人の温もりを感じられるマッサージやスキンシップ。誰かのために料理をする、手紙を書く、電話をかける――そんな小さな行為すべてが、「孤立しない脳」をつくる材料になるでしょう。
セックスは、そのひとつのかたちにすぎません。脳に必要なのは、「実体験」ではなく「実感」です。
便利さと孤立が進むこの時代だからこそ、“誰かと生きている”という感覚を、大切にすることが脳にも、心にも、そして社会そのものにも、じんわりと効いてくるのではないでしょうか。
そう考えると、最近流行っている「推し活」も、“誰かと生きている”という感覚を生み出すことで、結果的には様々な健康を守っているのかもしれません。















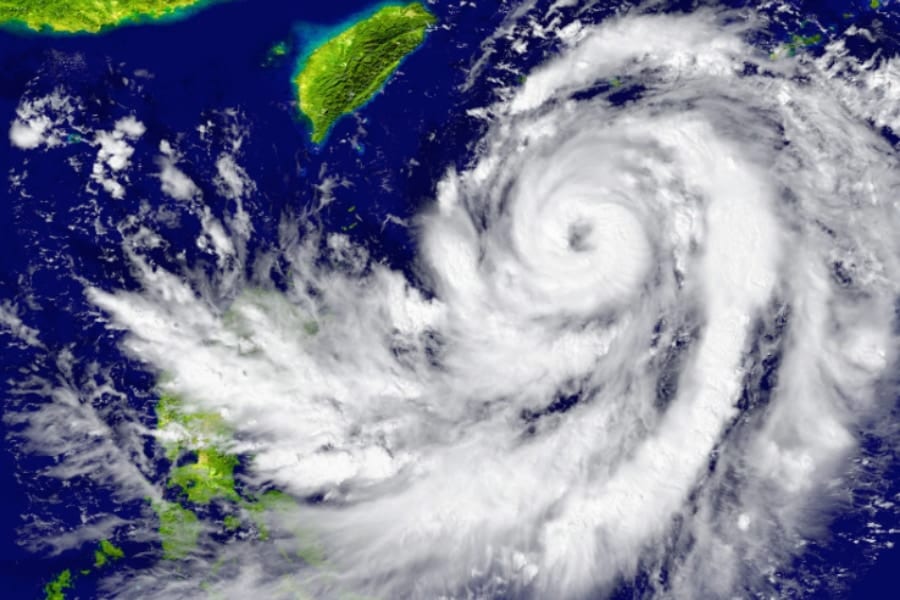



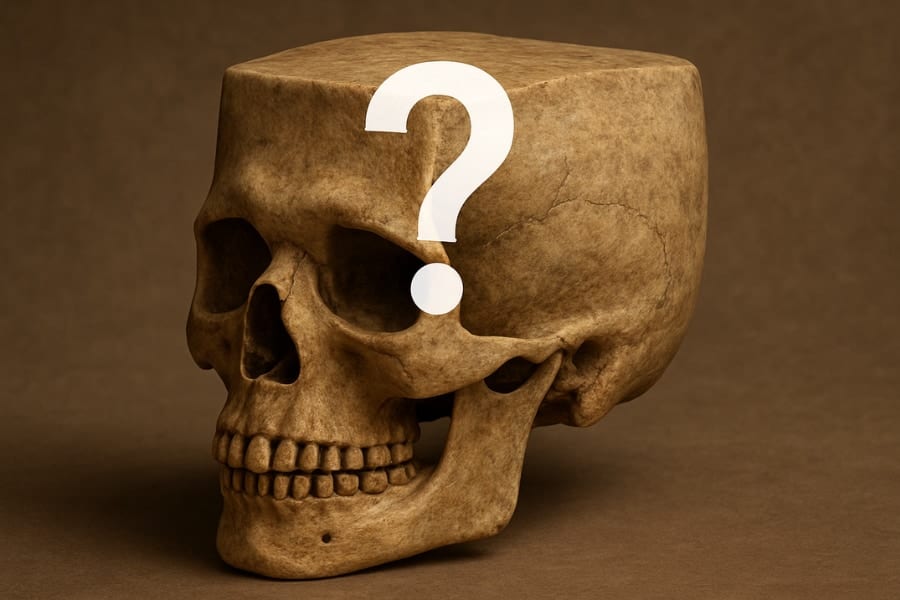
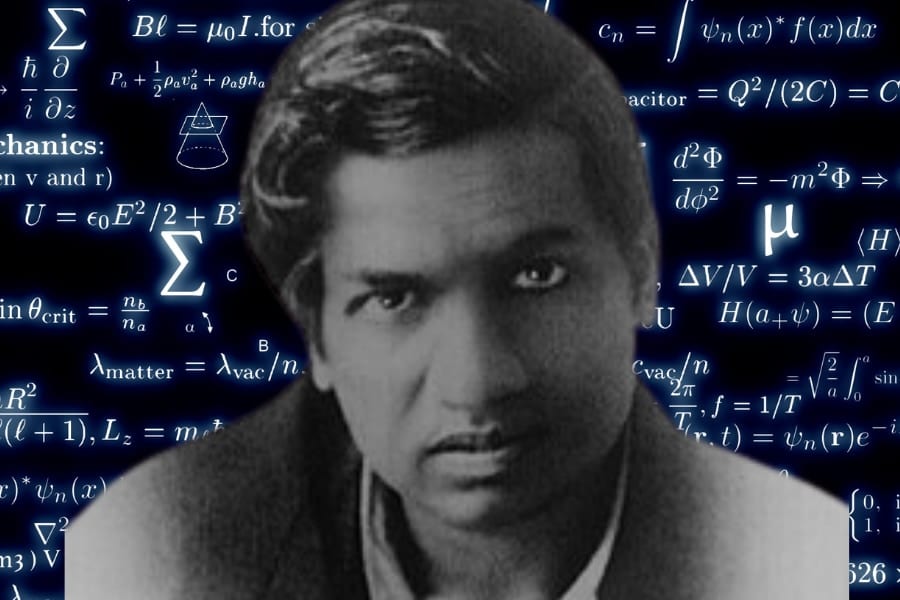












![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




























あ、あの…その…自慰…いえ…何でもありません。
じいじゃ効果ないどーぱみんだけ
せろとにんとか色々出るッスよ
理論上は…………
統計的に相関がみられるからって、
因果があるかのようにみなすのは、はたして科学なんだろうか?