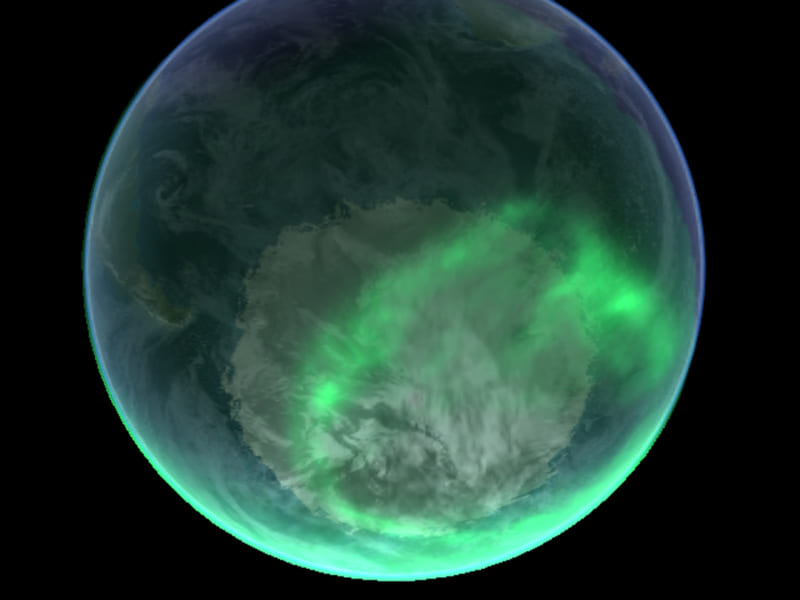3つのリズムを同時に測ると、見えてきた“心のズレ”

今回の研究で研究チームが挑戦したのは、体内リズムのズレを「正確に、同時に、個別に」測定することでした。対象となったのは、気分の不調を抱える69人の若者と、対照群となる健康な19人です。
研究チームが着目したのは、体内時計の中でも特に重要とされる3つのリズムです。
1つ目は、「メラトニン(melatonin)」と呼ばれるホルモンの分泌時刻です。これは、夜になると分泌される“眠気のホルモン”で、「脳が夜と認識し始めるタイミング」の目安になります。
2つ目は、「体温のリズム」です。人間の体温は24時間のうちで上下し、深夜から早朝にかけて最も低くなります。研究では深部体温が最低になる時刻(core body temperature nadir)に着目し、体がどのタイミングで“休息モード”に入っているか調べています。
3つ目は、「コルチゾール(cortisol)」と呼ばれるホルモンの分泌パターンです。これは目覚めとともに分泌が高まり、活動を助ける役割を持つホルモンで、「体が朝の始まりをどう感じているか」を読み取る手がかりになります。
研究ではこの3つのリズムがどれだけズレているかを、個人ごとに詳細に測定しました。
そのために、研究チームは大がかりな実験を行いました。参加者は自宅で数日間、腕時計型のセンサーで日常の活動や睡眠を記録したあと、夜通しのラボ観察に参加しました。
ラボでは、夜間に一定の明るさと温度を保った環境下で、一晩かけて30分ごとの唾液サンプルを採取し、そこからメラトニンとコルチゾールの分泌パターンを測定しました。さらに、参加者が飲み込む小型の体温センサー(Equivital LifeMonitor)を使い、体温の変化をリアルタイムに記録しました。
こうして得られたデータから、3つの生理リズムの時間差が分析されました。
その結果、うつ症状のある若者の約23%、つまり4人に1人が、3つのリズムの間に通常の範囲を超えたズレを示していることがわかりました。
とくに注目されたのは、体温リズムと気分症状との関係です。
体温の最低点が他のリズムと比べて極端に早く訪れる人ほど、うつの症状が強い傾向が見られました。つまり、「体はもう休息モードなのに、脳がまだ眠る準備をしていない」といった体の中での“すれ違い”が、気分の不調と結びついている可能性があるのです。
一方で、リズムのズレ方は人によって大きく異なっていました。メラトニンだけが遅れている人、コルチゾールのピークが遅い人、体温だけが早まっている人など、ズレのパターンは一律ではありませんでした。
この結果は、これまで単に「夜型」や「寝付きや寝覚めが悪い」などの曖昧な表現をされていた症状について、重要な見直しを迫るものです。
今回のように体内の複数のリズムを同時に測定することで、ズレのパターンが人それぞれ違うことが明らかになり、そのズレ方が、うつなどの精神状態とも深く関係している可能性が示唆されたのです。
「体内時計」は外の時間とのズレという意味で単純に表現されていましたが、「体内リズムごとのズレ方」が、心の調子に影響を与えるひとつのカギになるかもしれません。































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)