今回の結果から示される、気分を安定させる方法

今回の研究で、体内時計に関わる3つのリズム――メラトニン、コルチゾール、体温――を同時に測定したところ、これらが互いにずれている「体の中の時差ぼけ」が、気分の落ち込みと関係している可能性が示されました。
とくに注目されたのは、「体温のリズム」です。体温の最低点が、メラトニンやコルチゾールのタイミングと大きくズレている人ほど、うつ症状が強い傾向が見られたのです。
これは、体温のリズムが他の生理リズムと“足並みをそろえられなくなっている”ことが、心の不調に影響しているかもしれないことを示しています。
では、体温のリズムを整えるにはどうすればいいのでしょうか? 研究チームはこの点について直接介入を行ったわけではありませんが、過去の知見や体温リズムの性質をふまえると、次のような生活習慣が有効だと考えられます。
まず、朝に体温をしっかり上げることが大切です。起きてすぐに光を浴びることは、脳の体内時計をリセットし、体温を上昇させる重要な刺激になります。これは、体温リズムの“出発点”を整えるうえでとても効果的です。
次に、体温が自然に下がるような夜の過ごし方も意識しましょう。寝る1〜2時間前にぬるめのお風呂に入って体を一時的に温めることで、その後に体温が下がりやすくなります。
就寝の少し前にお風呂に入るとよく眠れるという話はよく聞きますが、そこにはこうした体温のリズムを整える効果も関係していると考えられます。
そのため、単に眠りにつきやすくなるというだけでなく、この“体温の下降”が、リズムの正常な夜間モードを後押し、体内で起きる時差ボケも防止してくれる可能性があるのです。
そして何より、起きる時間をできるだけ毎日そろえることが、体温リズム全体を安定させる基本です。
今回の研究が示したように、「眠れているかどうか」だけではなく、「体の中のリズムが整っているかどうか」も、気分に影響している可能性があります。
体温リズムは、意識すれば生活の中で整えられる数少ない体内時計のひとつです。朝の光、夜の入浴、毎日の起床時間。どれも小さなことですが、心の調子を立て直すきっかけになるかもしれません。































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




















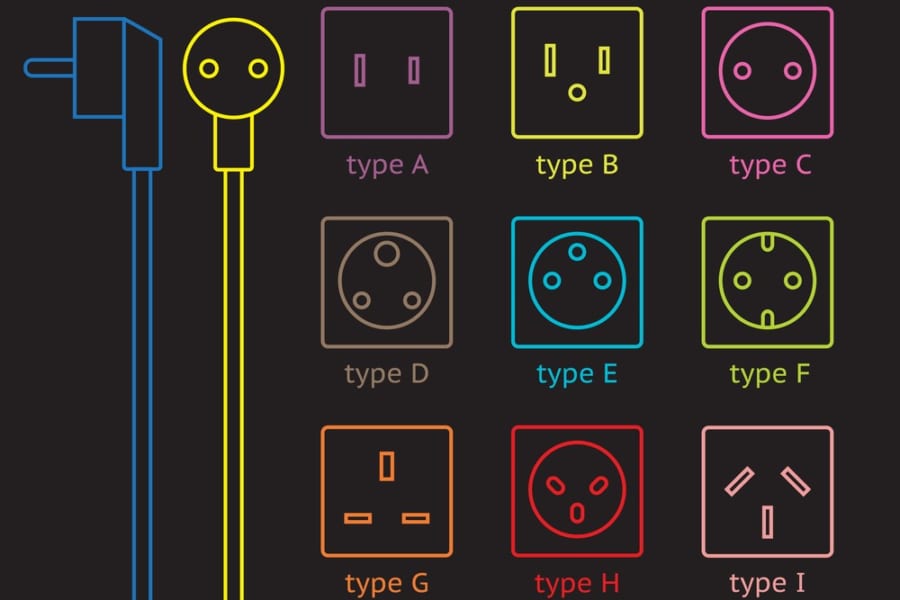
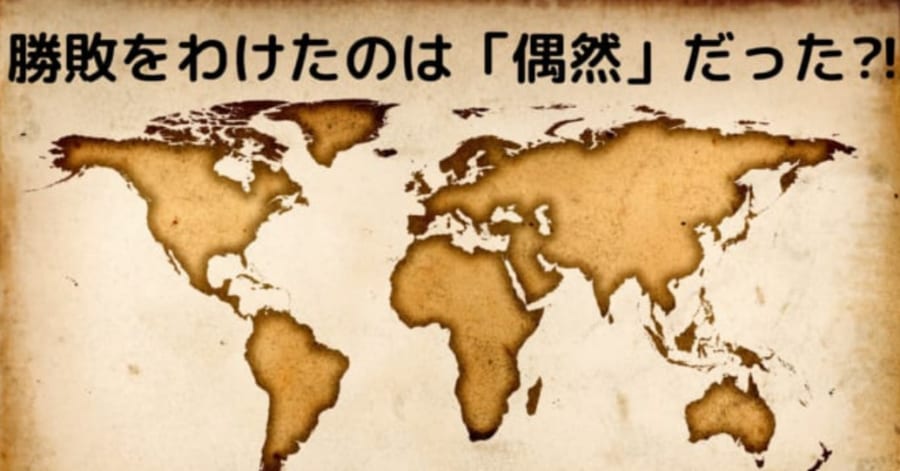






人間は夜に睡眠、昼間に活動するというサイクルで生きる動物なので、何らかの外部の影響で昼夜逆転すると本来のリズムで動く体内時計の時間がずれが生じて、自律神経が乱れてあらゆる不調を起たします。