3人の子どもが同じ性別であれば4人目も同じ性別が生まれる確率は約60%

カップルや母体の条件によって、生まれやすい性別があるのか?
この謎を解明するために、研究者たちは分析の単位を個々の出産から各母親に切り替えました。
従来の研究の多くは出生ごとにデータを集計し、性別とさまざまな要因との関連を探していました。
しかし、それでは家族内に存在するかもしれない性別の偏りパターンが見逃されてしまう可能性があります。
そこで研究チームは、家族(母親)ごとに見たときに、子どもの性別が本当に公平なコイントス的な確率分布に従うのか、それとも母親ごとに偏り(ばらつき)があるのかを検証することにしました。
さらに、もし偏りがあるとすれば、どのような要因が「男の子ばかり」や「女の子ばかり」をもたらすのか(例えば遺伝的な体質なのか、母親の年齢などの属性なのか)を探ることにしました。
調査にあたってはまず、各母親について子どもたちの性別の並びを分析し、その分布を「期待されるランダム分布」と比較しました。
その結果、子どもの人数(きょうだいの数)が多い家庭ほど、性別の分布が単純な50%の期待値からズレていることが明らかになりました。
言い換えれば、家族内で子どもの性別が偏って生まれているケースが、偶然では説明できないほど多く存在するのです。
統計的には、この分布は従来考えられていた単純な二項分布(各出生が独立で50%の確率)ではなく、各家庭ごとに確率が異なる「ベータ二項分布」に適合すると分析されました。
これはまるで「各家庭ごとに重りのついた(偏った)コインを投げているようなもの」だと研究者らは表現しています。
ある母親はやや男の子が生まれやすいコイン、別の母親は女の子が出やすいコインを持っている、といったイメージです。
この偏りを端的に示すため、研究では「次の子が同じ性別となる条件付き確率」を計算しました。
モデルによれば、最初の2人が同じ性別だった家庭では、3人目も同じ性になる確率が約54%程度と、やや50%を上回りました(男児2人の場合は3人目も男児、女児2人の場合は3人目も女児)。
さらに、3人連続で同じ性別だった家庭では、その確率が一層高くなり、男児が3人続いた家庭では4人目も約61%、女児が3人続いた家庭では4人目も約58%という予測が得られました。
実際のデータでも、4人目以降までいる家庭数は限られるものの、概ね同様の傾向が確認されました。
この結果は、「一度出たコインの目に次もなりやすい」という家族内相関の存在を示唆しています。
一方で、データには「親の意思による子どもの人数調整」も反映されています。
例えば「男の子と女の子を一人ずつ得たらそれ以上子どもはもう十分」と考えて、2人で打ち止めにする夫婦も多いでしょう。
実際、本研究でも2人きょうだいの家庭では「1人が男児、もう1人が女児」というパターンが他の組み合わせ(男男・女女)より有意に多いことが確認されました。
これは男女が揃った時点で出産をやめるカップルが多いことを反映したものと考えられます。
反対に、3人以上のきょうだいがいる家庭では同性ばかりの組み合わせが混合より増える傾向が見られました。
つまり「同じ性別の子が続いたので、違う性の子を求めてもう一人トライした」というケースもあれば、それでも結果的に同性が続いてしまった家族も多いわけです。
このように親の行動(望む性別の子どもができるまで産み続ける/両性が揃ったらやめる)は、家族内の性別パターンに影響を与えます。
この影響を取り除いて純粋な生物学的傾向を測るため、研究チームは各女性の「最後の出産」を除外する感度分析も行いました。
すなわち、各家庭がもう一人子どもを持つと仮定して分析することで、「打ち止め効果」(いわゆる“コレクター趣向”)を弱めたのです。
その結果、偏りの傾向はむしろ一層鮮明になり、統計的な有意性も高まったといいます。
これは、親の出産打ち切り行動が偏り現象を過小評価させていた可能性を示しています。
つまり、本来はもっと偏りやすい体質の母親であっても、途中で出産をやめてしまえば「偶然両方産んだだけ」のように見えてしまうからです。
このように、子どもの性別が家庭ごとに異なる『偏り』を持つことが、統計的にも明確になりました。
しかしそうだとすると、いったい何が母親ごとに生まれやすい性別を決めているのでしょうか?




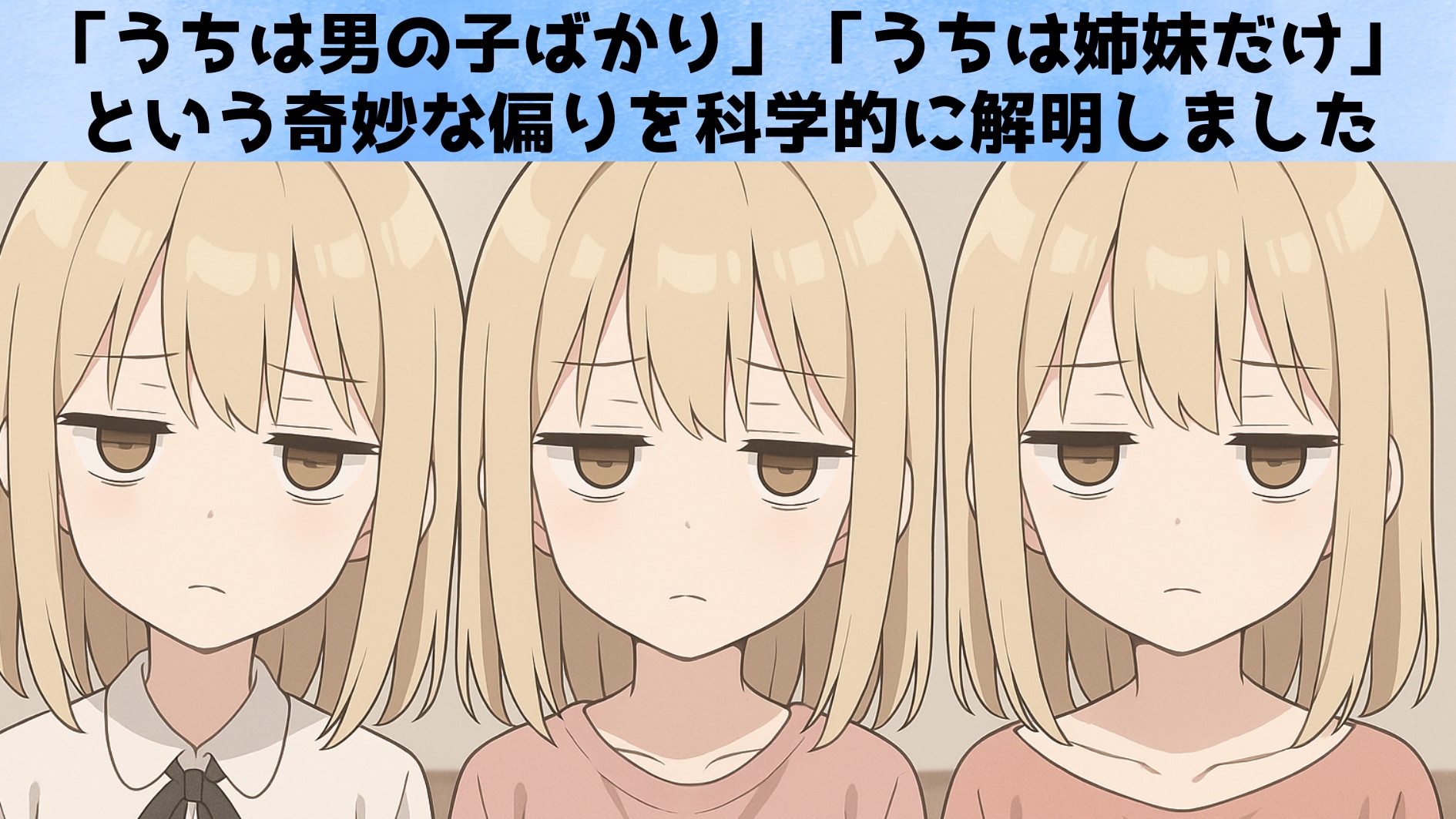

























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























