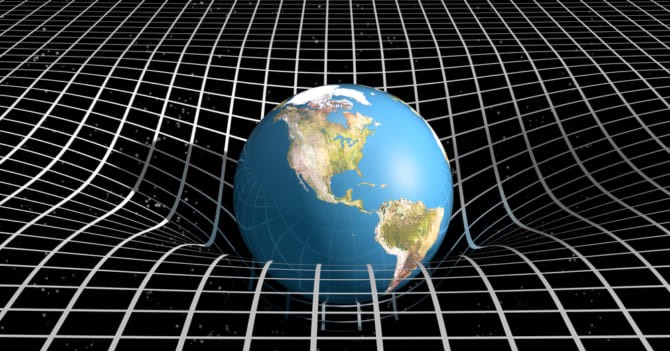人間の血を「飲む蚊取り線香」状態にする薬

新しい薬や治療法が考え出されたとき、それが本当に効果的で安全かどうかを確認するために、科学者たちは入念な実験を行います。
今回の研究で行われた実験は「クラスター無作為化比較試験」という方法でした。
これは簡単に言うと、地域をいくつかのグループ(クラスター)に分けて、各グループごとに異なる薬や方法を使い、その後の効果を比べる方法です。
「無作為化」とは、偶然に任せてグループを割り当てることを指します。
この方法によって、特定の条件に偏りが出ないよう公平に比較が行えるのです。
研究が行われた場所は、ケニアのクワレ郡という地域でした。
ここはマラリアの感染がとても多い地域として知られています。
この地域では以前から蚊を防ぐための「蚊帳」の普及率が85%と高く、実際に使っている家庭も約77%に上っていました。
しかしそれでもなお、多くの人がマラリアに感染し続けていたため、新しい対策の必要性がありました。
今回の実験では、クワレ郡に住む約2万9000人が対象となりました。
研究チームは、地域のコミュニティを全部で84のグループに分けました。
その後、それらをランダム(無作為)に2つの大きなグループに振り分けました。
一方のグループには、イベルメクチンという薬を月に1回、3ヶ月連続で飲んでもらい、もう一方のグループには「アルベンダゾール」という別の薬を同じ頻度で飲んでもらいました。
なぜ比較のためにアルベンダゾールを使ったのでしょうか?
それは、「薬を飲む」という行為自体が人の体調に何らかの影響を与える可能性があるためです。
例えば、「何も薬を飲まないグループ」と「薬を飲んだグループ」で比較すると、薬の効果とは別に「薬を飲んだ」ということ自体が影響を与えてしまい、薬の本当の効果がわかりにくくなる可能性があります。
アルベンダゾールはイベルメクチンと同じように寄生虫駆除には効果がありますが、蚊を殺す効果はありません。
そのため、薬を飲んだことによる影響を両グループで揃えることができ、「イベルメクチンの蚊を殺す効果」だけを明確に確認できるよう工夫されたのです。
研究では特に、マラリアの感染リスクが高いとされる5歳から15歳までの子どもたちの感染状況を詳細に調べました。
薬を飲み始めてから6ヶ月間、毎月子どもたちを検査してマラリアの感染の有無を確認し、それぞれのグループでどれくらいマラリア感染に差が出るかを比べました。
その結果、イベルメクチンを飲んだグループでは、アルベンダゾールを飲んだグループに比べて感染率が26%も低くなるという結果が得られました。
これは統計的な解析によっても確認された有意な差(発生率比0.74、95%信頼区間0.58~0.95、P=0.02)であり、単なる偶然の結果ではないことがわかっています。
つまり、この差は「実際にイベルメクチンが蚊を殺したこと」によるものである可能性が非常に高いと言えます。
さらに注目すべきは、この地域の住民の多くは既に蚊帳を使っていたにもかかわらず、イベルメクチンの効果がはっきり現れたことです。
これはイベルメクチンが、蚊帳で防ぎきれない屋外や昼間などの環境にいる蚊にも有効に作用したためと考えられます。
薬を効率よく配布できた地域ほど効果が高くなる傾向が見られたことも、この薬が広く実用化された場合の効果を予測する上で重要なポイントです。
一方、安全性についても慎重に検討されました。
薬を何万人もの人に配る場合には、予期しない副作用や健康被害が起きないかを厳密に調べる必要があります。
今回の試験では、イベルメクチンが半年間にわたり延べ5万6000回以上も投与されました。
その結果、深刻な副作用は一度も確認されませんでした。
一方で、軽度の副作用(頭痛やめまいなどの一時的な体調不良)の報告はありました。
その報告頻度はイベルメクチン群で投与100回あたり約6.2件、対照群では約3.8件と差があり、この差は統計的に意味のある増加(発生率比1.65、95%信頼区間1.17~2.34、P=0.005)でした。
ただし、この増加は一時的で軽い症状に限られており、命に関わるような深刻な問題や長期的な健康被害が増えたわけではありませんでした。
過去に世界中でこの薬が安全に使われてきた実績からも、イベルメクチンは引き続き安全に使用できる薬であることが確認されました。
しかし、この研究結果から新たな疑問も生まれます。
今回確認された26%という感染率の減少は、さらに規模を大きくして実施した場合にも同じように確認できるのでしょうか?
また、より多様な年齢層や妊婦など特にマラリア感染リスクが高い人々に対しても、この薬の安全性と有効性は確保されるのでしょうか?




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)