体外受精を基本的な権利に

今回の研究では、体外受精(IVF)によってすでに世界で1300万人以上(最大で1700万人)の赤ちゃんが誕生していることが明らかになりました。
これはとても大きな数字であり、体外受精という技術が、子どもを持ちたいと願う多くの人たちにとって、どれだけ大きな助けになっているかを示しています。
もはや体外受精は、特別な人たちだけの医療ではありません。
たとえば、オーストラリアでは全体の約6%、デンマークでは約10%の赤ちゃんが体外受精で生まれているとされています。
(※2022年の確定データでは日本でも約10%が体外受精で生まれていると報告されています。彼らが小学生になったら、30人クラスのうち3人は体外受精を介して生まれてきたことになります)
これは、体外受精が「最後の手段」ではなく、「当たり前の選択肢」として広がっていることを意味します。
しかも、体外受精を利用しているのは、夫婦だけではありません。
独身女性や同性カップルなど、さまざまな家族の形が広がる中で、IVFは新しい命を迎えるための大切な手段になっています。
研究チームは、この技術が医療面だけでなく社会的にも大きな意味を持つと強調しています。
実際、技術もどんどん進歩しています。
昔は双子や三つ子が多く生まれるリスクもありましたが、今では1回の治療で1つの受精卵だけを使う方法が広まり、双子以上の出生率は3%未満にまで下がっています。
お母さんや赤ちゃんの安全にも配慮された進化です。
一方で、課題もあります。体外受精は高度な技術と設備が必要で、治療費も下がったと言っても高額です。
そのため、お金に余裕がある人や、制度が整った国に住む人だけが受けやすいという現状があります。
たとえば、日本では2022年から保険が使えるようになり、以前よりは身近になりましたが、世界にはまだ治療を受けたくても受けられない人がたくさんいます。
研究チームは、「体外受精はすべての人に平等に与えられるべき“権利”である」と主張しています。
もうひとつの問題は、「体外受精があるから、いつでも子どもができる」と考えてしまう人がいることです。
でも実は、年齢が上がるにつれて卵子の質や数は減ってしまい、体外受精の成功率も下がってしまうのです。
たとえば、35歳の女性で体外受精の成功率は約30%ありますが、40歳になると約15%、42歳では約10%にまで下がってしまいます。
つまり、「年をとっても大丈夫」と思っていると、うまくいかずに心や体、お金にまで大きな負担がかかってしまうことがあるのです。
体外受精はすばらしい技術ですが、それだけに頼るのではなく、「子どもを持ちたい」と思ったときに社会がしっかり支えるしくみも必要となるでしょう。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)





















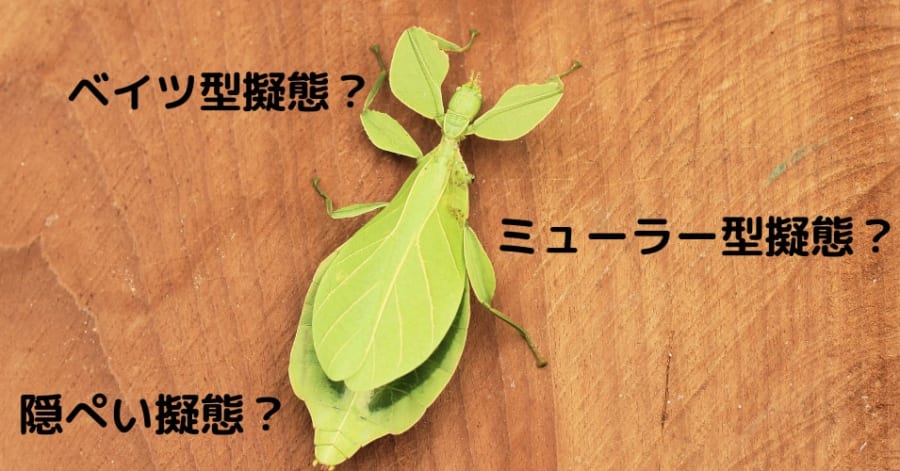






むしろ双子のほうが受け良さそうな気もしますけどそうでもないのですね。
私の母なんかは双子が欲しかったと言っていましたが。
クソDQNなんかのとこじゃなくて、欲しい人んとこにすんなり生まれてくれればいいのになあ
時間も金もかかるし母体は苦痛増えるし
赤ん坊が、天からの授かりものではなくテクノロジーからの選択的生殖となりつつあるんですね。
功罪あるでしょうからそれに社会がどう向き合うか気になる所です。