スマホ依存の“落とし穴”、心の隙間を埋めるはずが逆効果に?
では、なぜ夜型の人ほどスマホやSNSにのめり込んでしまうのでしょうか。
研究によれば、夜型タイプの若者は、「不安」や「孤独」を紛らわせるためにスマートフォンやSNSに頼る傾向があることが分かっています。
たとえば、
・眠れない夜、手持ち無沙汰でSNSを開く
・寂しさを感じたときに、誰かの投稿やメッセージを求めてスマホを手に取る
・通知が来るたび「誰かとつながれるかもしれない」と期待してしまう
一時的には、スマホやSNSを使うことで気分がまぎれるかもしれません。
しかし、そこには「悪循環」が潜んでいます。
研究者は「夜型の若者が心の寂しさを埋めるためにテクノロジーを利用すると、かえって孤独感や不安感が強まってしまうケースが多い」と警告します。
実際、
・スマホやSNSに頼りすぎると、リアルな人間関係がますます希薄に
・依存的な使い方が続くことで、学業や生活の質が低下
・スクリーンタイムが増えることで、睡眠の質も悪化し、さらに心身の不調が深まる
という負のスパイラルが生まれるのです。
この「心の隙間を埋めるためのスマホ利用」が、知らず知らずのうちに「心の傷口を広げてしまう」――それが現代型依存の怖さなのです。
スマートフォンやSNSは、私たちの生活に欠かせない便利なツールです。
しかし、不安や孤独を癒す“心の薬”ではありません。
特に夜型タイプの人々にとっては、「社会とのズレ」や「心の孤独」を抱える中で、スマホやSNSが危険な慰めとなりやすいというリスクが、今回の研究で明らかになりました。
研究者たちは「依存を防ぐには、単にスマホの利用時間を減らすだけでなく、不安や孤独感そのものにアプローチする支援が重要」と指摘しています。











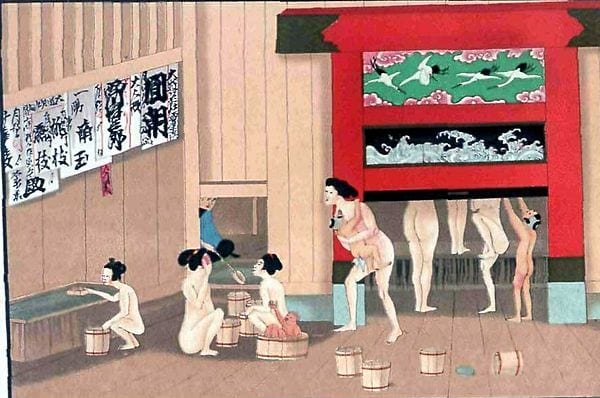


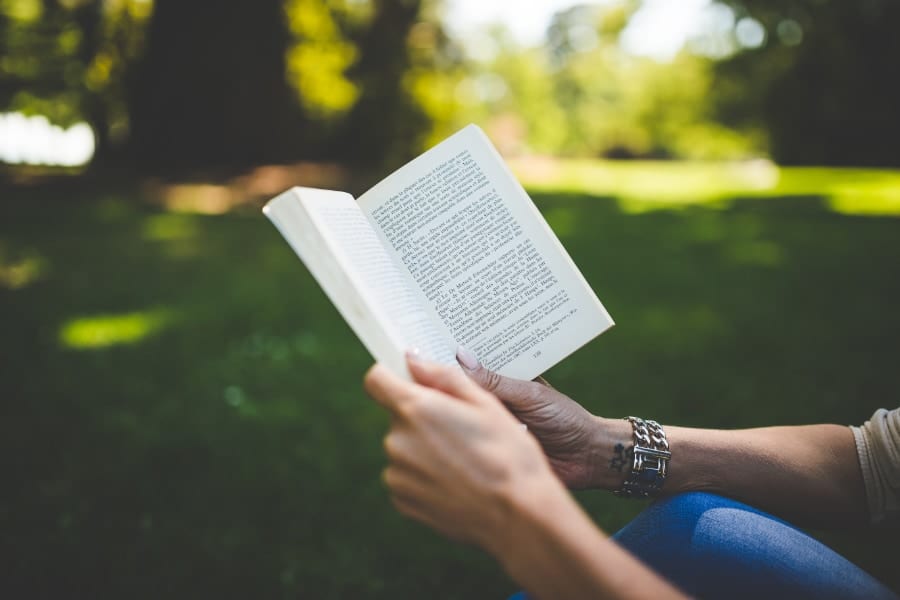
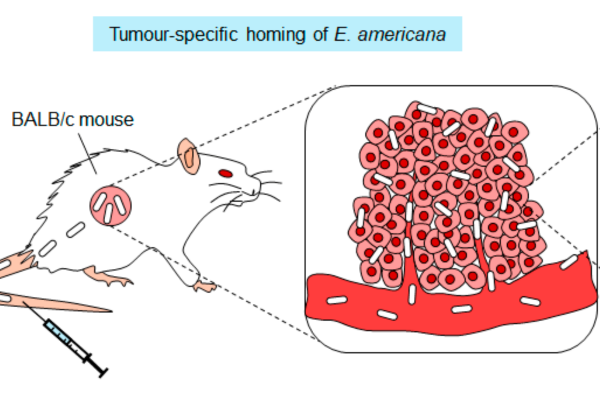
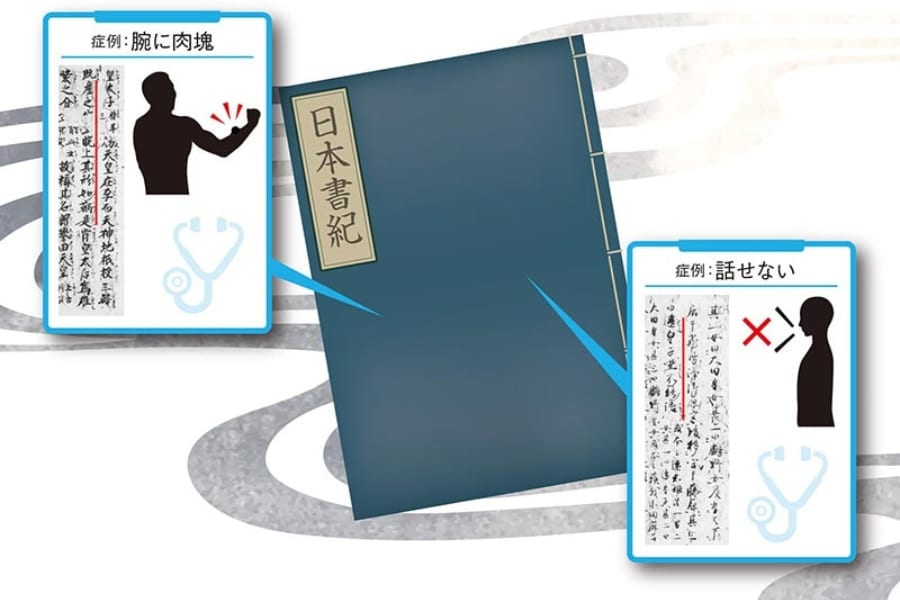












![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)







![流星のロックマン パーフェクトコレクション -Switch【Amazon.co.jp限定】特典 アイテム未定 & 【早期購入特典】『アレンジBGM4曲』+『「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター』DLC印字チラシ[有効期限:2027年3月27日(土)まで] 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUH0kspfL._SL500_.jpg)













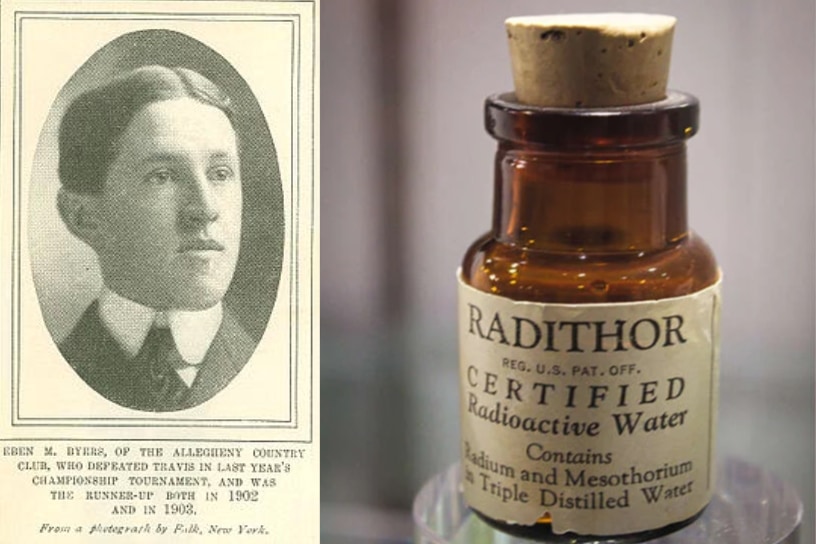







かと言って代わりになるものがないのでは彼らの不安は解消されませんしね。
運動はネット依存の対症療法として効果がありますが、社会がオンライン化、個人化している中で孤独を埋める根本解決は難しいですね…