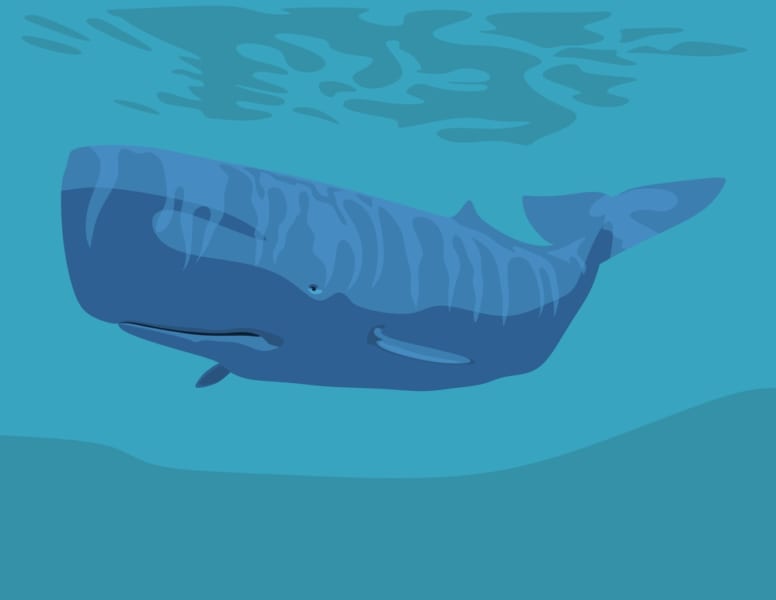退職後の幸福度は「所得」や「特定の要素」で異なる
研究の最大の発見は、退職によって心の健康が全体的には改善するものの、その上がり方や持続のしかたは人によって大きく異なるということでした。
まず、高所得層では、退職の前後では大きな変化は見られませんでしたが、退職した年だけ幸福感が大きく上昇する現象が観察されました。
そしてその後は、安定した状態が続きます。
中所得層では、退職前からじわじわと心の健康度が上がり始め、退職後も緩やかに改善が続くという結果になりました。
ただし、肉体的に負担が大きい仕事をしていた人は、退職の過程で気分が落ち込むリスクがあり、メンタルの改善が限定的になる傾向がありました。
低所得層では、退職後に一度は幸福感が上がるものの、2年半ほどでピークを迎え、その後低下していく傾向が明らかになりました。
「退職後の最初だけ幸福感が高まる現象」が見られたのです。
特に、低所得層の中でも女性や独身者は、退職後の心の健康が著しく低下しやすい傾向が見られました。
ちなみに、高所得層や中所得層では、もともと心の健康度が高い人ほど、退職後の伸びしろが小さくなる傾向も見られています。
逆に、もともと心の健康が不調だった人は、退職による恩恵が大きいことも示唆されました。
こうした研究結果は、「退職したら必ずバラ色の老後が待っている」という定年神話に疑問を投げかけるものです。
本研究は、17年分、1500人以上を追跡したという点で非常に信頼性が高いですが、いくつか限界も指摘されています。
例えば、高所得層のサンプル数が少ないこと、低所得層の参加者が女性に偏っていること、退職理由(自発的か非自発的か)が区別できないこと、オランダ特有の手厚い年金制度が前提となっていることなどがあります。
それでも、退職が必ずしも全員の幸福に直結しないこと、所得や性別、婚姻状況、仕事の負担によって老後の心の健康リスクが大きく異なること、特に低所得層の女性や独身者、肉体労働経験者は退職後に集中的なサポートが必要であることが明確になりました。
定年退職後に私たちのメンタルがどうなるかは、一様ではありません。
だからこそ、自分の状況を見極めてサポートを受けつつ、自分のスタイルで退職後の生活を楽しんで行く必要があるのです。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)