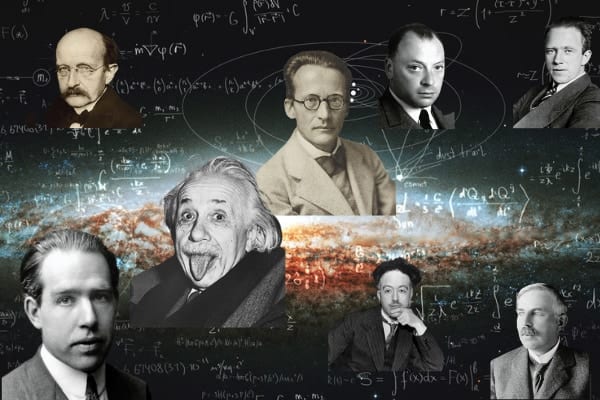中性子の寿命に関する謎
物理学の謎は色々あるのだが、一般的にはあまり知られていない。
その内の1つが、中性子の寿命の謎だ。
中性子、お前死ぬのか? と思うかもしれないが、中性子は原子核内では安定しているが、原子核の外に出され、自由中性子になると15分程度で崩壊して電子や反ニュートリノを放出しながら陽子に変換されてしまう。
これをβ崩壊という。

自由中性子がβ崩壊を起こして陽子に変わるまでの時間がいわゆる中性子の寿命だ。
現在、中性子寿命は二つの実験手法によって、非常に高い精度で測定されている。
一つは中性子を磁場中に閉じ込めて崩壊する頻度を測るもので、その寿命は879.4±0.6秒(大体14分39秒)だ。
そしてもう一つの実験は、中性子をビームにしてパイプ中を飛行させ、その崩壊頻度を測る方法で、寿命は888.0±2.0秒(大体14分48秒)とされている。
これらの実験結果はどちらも精度が高く、複数の研究チームによりそれぞれ何度か測定が個別に行われているのだが、なぜか約9秒近い差が出てしまっている。
物理学の話題となると、普段はナノ(10億分の1)秒単位で時間がずれても大問題と言われることが多い。9秒なんて、素粒子どころか小学生が50メートル走れる時間だ。
いくらなんでもずれ過ぎだ。
物理学者たちはどちらの実験についても信頼性は高いと考えており、これは非常に不思議な問題となっている。
なぜ、中性子の寿命は、測定方法によってこんなにもずれが出てしまうのだろうか?































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)