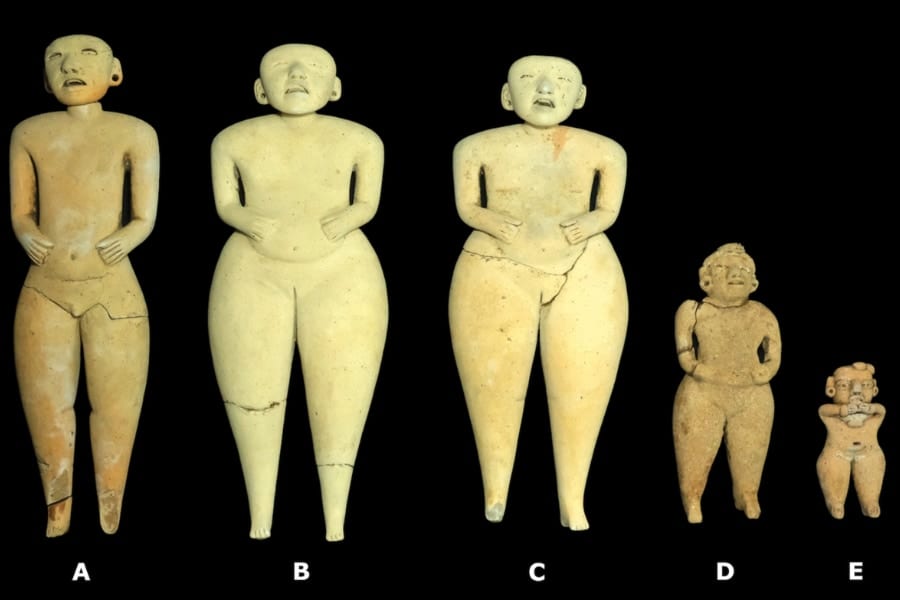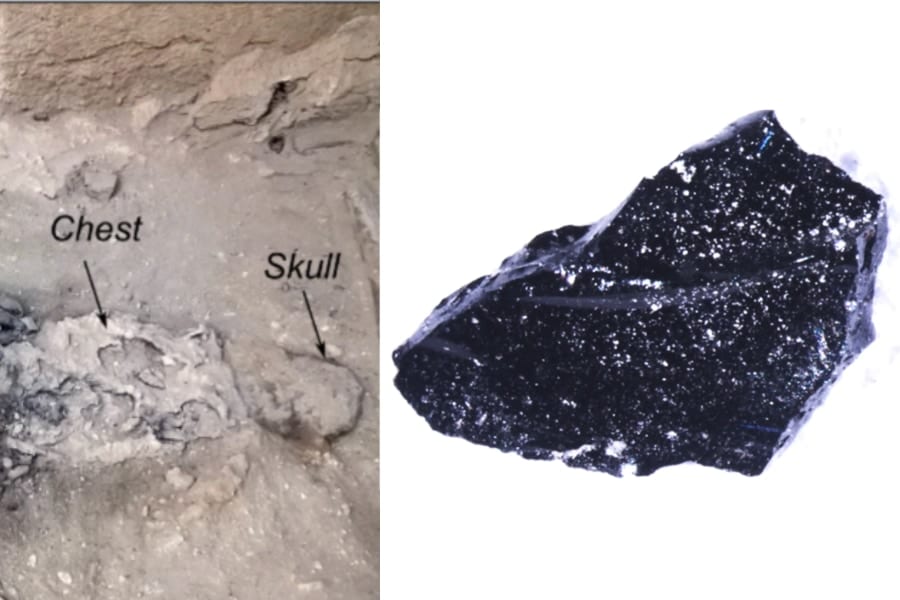第6代・乾隆帝に関連するシンボルが描かれていた

花瓶は高さ約60センチと大きく、下地は濃い青色で塗られ、その上に金と銀で装飾が施されています。
英オークション会社ドレウィッツ(Dreweatts)のアジア陶磁器・美術品の専門コンサルタント、マーク・ニューステッド(Mark Newstead)氏によると、花瓶には、清の第6代皇帝・乾隆帝(在位:1735〜1796)に関連するシンボルが刻まれているという。
特に、金で装飾された「雲・鶴・扇・笛・コウモリ」は、乾隆帝が信仰していた道教のシンボルであり、「幸運」と「長寿」に関連するといいます。


また、花瓶に使われている金と銀の組み合わせについては、「技術的に非常に難しく、それがこの花瓶を特別で希少な一品にしている」と話しました。
この技法は、かつて中国東南部・景徳鎮にあった陶磁器工場の監督官である唐英(1682〜1756)という人物が考案したと考えられています。

「この花瓶はおそらく、紫禁城(しきんじょう、北京市にある明・清朝の旧皇宮)か、皇帝が所有する他の宮殿のいずれかに置かれていたのでしょう」と、ニューステッド氏は指摘します。
どんな経緯でイギリスまで運ばれたのか?
花瓶がイギリスにたどり着いた経緯は、多くが不明のままです。
最初に所有していたのはイギリス人の外科医で、1980年代初頭に購入したと推測されています。
その外科医は1970年代以降、イギリス中部の田舎町でバイヤーをしていたことがわかっています。
彼が亡くなった後、花瓶は現在の持ち主である息子に受け継がれました。
しかし、親子とも花瓶の真の価値には気づかず、息子は自宅のキッチンに何年も飾っていたとのこと。
ちなみに、この持ち主とニューステッド氏が知り合いで、花瓶の存在を知ったといいます。

ニューステッド氏は、花瓶の経緯について、19世紀か20世紀初めに中国からイギリスに運ばれたと見ています。
第一の可能性は、1856〜1860年に清と英仏の間で勃発した「アロー戦争(第二次アヘン戦争)」で、イギリス軍が清朝の美術品を略奪した際に持ち運ばれたと考えられます。
第二の可能性は、1900年に清の民衆によるヨーロッパ列強への反発から起きた「義和団事件」です。
これを機に、イギリス・フランス・ドイツを筆頭とするヨーロッパ諸列強が清に出兵し、北京を占領。このときに、花瓶を含む清の美術品が略奪されたのかもしれません。
あるいは第三の可能性として、花瓶が皇帝から部下の役人に贈られ、その家族の中で代々受け継がれたものの、20世紀初めの清の情勢悪化(経済苦境)で売却したという説です。
その後、花瓶は持ち主を転々として、イギリスにたどり着いたとも考えられます。

花瓶は5月18日、ドレウィッツ主催のオークションにて、約180万ドル(約2億3000万円)で落札されました。
まさか自宅のキッチンにあった花瓶にこれほどの高値がつくとは、持ち主も予想だにしなかったでしょう。
今回のように、清王朝の美術品には、世界中に散らばって、所在不明になっているものが数多くあると見られます。
もしかしたら、皆さんのご実家にも、清朝のお宝が眠っているかもしれません。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)