高嶺の花ではあったものの、決して手の届かない娯楽ではなかった相撲見物

このように江戸の庶民が相撲を観戦するというのは、単なる娯楽というよりも一大イベントだったようです。
それでは相撲見物には、どれくらいの費用がかかったのでしょうか。
『文政年間漫録』を参考にすると、例えば、野菜を売る棒手振の日収は約400文(1文=32.5円とした場合、13,000円程度。なお江戸時代と現代では物の価値が大きく異なっており、単純に比較することが難しいので注意する必要がある)。
これに対して、毎日の支出である米代や味噌代、子供のお菓子代を差し引くと、残るのは100〜200文(3250~6500円)程度です。
さらに、雨の日には商売ができないことも考えると、この収入は実に不安定です。
一方で、大工のような職人はやや安定しており、日収は540文(17,550円)ほど。
しかし、家賃や食費、薪代などを支払った後に残る金額は棒手振とさほど変わらず、やはり100文程度です。
桟敷席の見物料は、当時の記録を元に4000文(130,000円)程度と推測されています。
これを一人で支払うとなると、中下層の庶民にとっては約40日分の余剰金をため込む必要があり、到底手軽な娯楽とは言えません。
しかし、桟敷席は一間ごとの価格設定であったため、例えば8人で費用を分担すれば一人あたり500文(16,250円)です。
これでも5日分の余剰金が必要であり、やはり高嶺の花であったことは否めませんが、決して庶民にも手が届かないものではなかったことが窺えます。
そうした状況を背景に、庶民はどうにかして相撲見物を楽しもうと工夫を凝らしたことでしょう。
これが単なる費用の問題ではなく、江戸っ子の心意気や人々の付き合いをも巻き込んだ「特別な一日」を生み出したことは容易に想像できます。




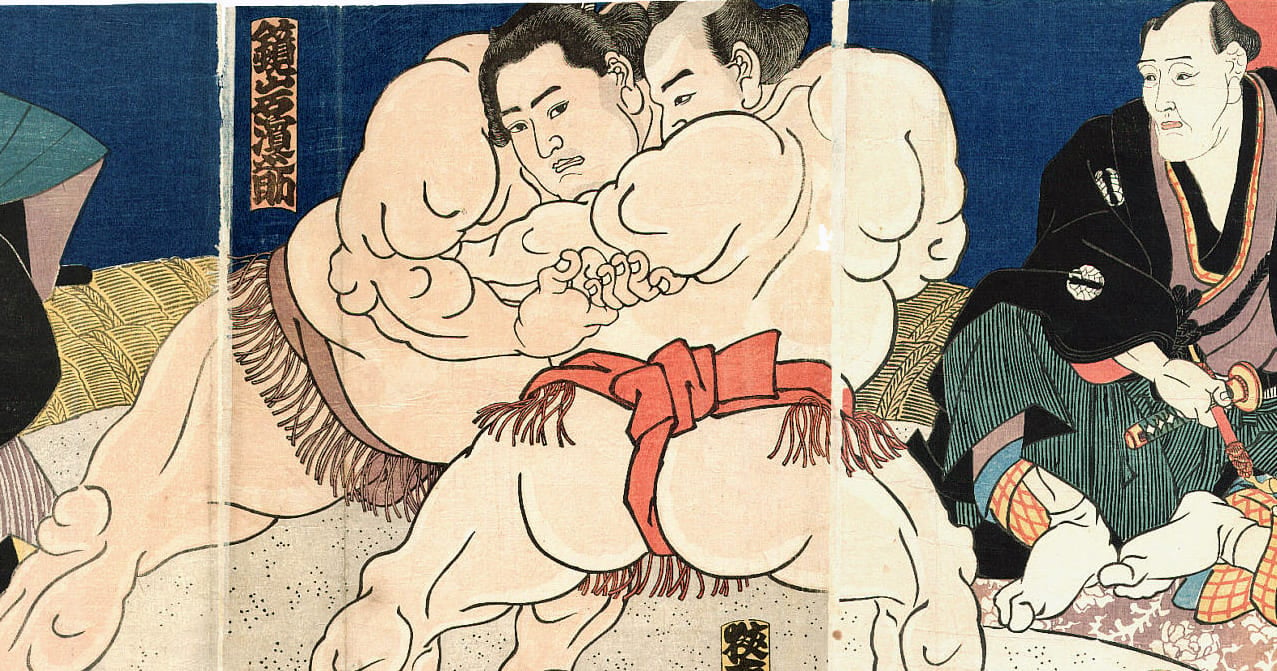
























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























