「何を見るか」ではなく「どう見るか」が鍵
さらに興味深いのは、庭園内のどのオブジェクトに注目したか(橋、水、植栽など)と、心拍数の変化には明確な関連がなかった点です。
つまり、「何を見たか」ではなく、「どう見たか」が決定的だったのです。
研究では、無鄰菴では視線が遠近、上下左右にわたって立体的に動いていたのに対し、学内の日本庭園では視野が限定され、視線も前方中心に偏っていました。
特に無鄰菴では、水の流れが斜めに配置されており、視線を自然と左右に誘導する設計がなされています。
また、背後の東山の借景や剪定された木々の隙間から見える遠景も、視線の広がりを後押しします。
このように、計算された空間設計と丁寧な維持管理が、「見る」という行為そのものを変え、それが心と身体にまで影響を与えるのです。
実際に、都市計画を学ぶ学生(日本庭園に詳しくない)でも、無鄰菴では大きなリラックス効果が確認されました。
むしろ、初めて見る人ほど効果が高い可能性すらあります。
美しい日本庭園を見るだけで心が癒される—。
それは偶然ではなく、人の視線をデザインとしてコントロールする、繊細かつ巧みな空間演出によって生まれる「設計された癒し」なのです。

この研究は、単に日本庭園の魅力を再確認するだけではありません。
無鄰菴のような設計と手入れが行き届いた空間は、非薬物的なストレス対策としての可能性を秘めています。
しかも、それは広大な敷地や高価な設備が必要なわけではなく、視線を動かしたくなるような空間デザインと、わずかな自然の導線で実現可能なのです。
チームは今後こうした庭園空間が病院や高齢者施設などの医療福祉現場で応用される可能性を示唆しています。

























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)




















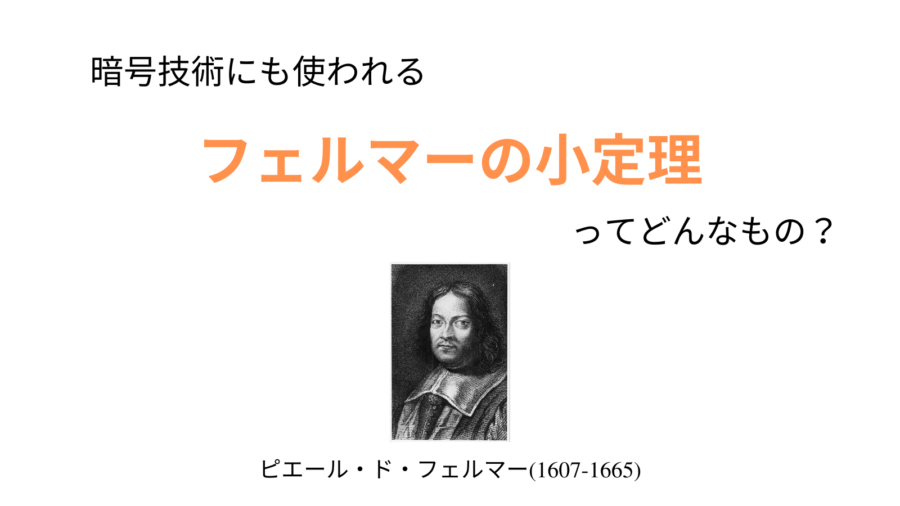







メンテナンスとかに費用も人も技術もいりますからどこでもいつでもというわけにはいかない気がしますね。
「視線が左右に活発に、そして広範囲に動」くことが重要な条件なら、横に広がりを持つ風景・景観であればよいわけで、日本庭園である必要はありませんね。
今度はVRゴーグルで様々な風景を見せて比較してみると面白いかも。
>>視線が左右に活発に、そして広範囲に動くことが重要
うむ、なんかソシャゲのエロティックな広告とか貼っても使えそう