ゼロ光子が拓く超低温テクノロジーの地平
今回の成果は、物理学者たちに「何もないことも、実はとても意味がある」というメッセージを突きつけています。
共同第一著者のジャック・クラークさんも「何かが存在しないと気づくことは、その存在に気づくのと同じくらい多くを語ってくれるのです」と述べており、日常生活でも雨が降っていないことや鍵が見当たらないことから多くの情報を得ているのと同じだと説明しています。
このゼロ光子検出という量子計測の技術を使えば、対象の振動エネルギーを従来の限界を超えて下げられる可能性が示されたわけです。
今回の研究論文はアメリカ物理学会の学術誌「フィジカル・レビュー・レターズ (Physical Review Letters)」に2025年2月に発表され、量子測定と制御の分野に新たな道を拓く成果として注目されています。
研究チームは「ゼロ光子検出によって量子系を基底状態まで冷やし込むことで、量子コンピューターや量子ネットワークの開発、さらには物理の基本法則の検証にも役立つだろう」と期待しています。
今後、この「何も見えなかった」ことを利用する量子のトリックが、様々な分野でどのように応用されていくのか、さらなる研究が待たれます。




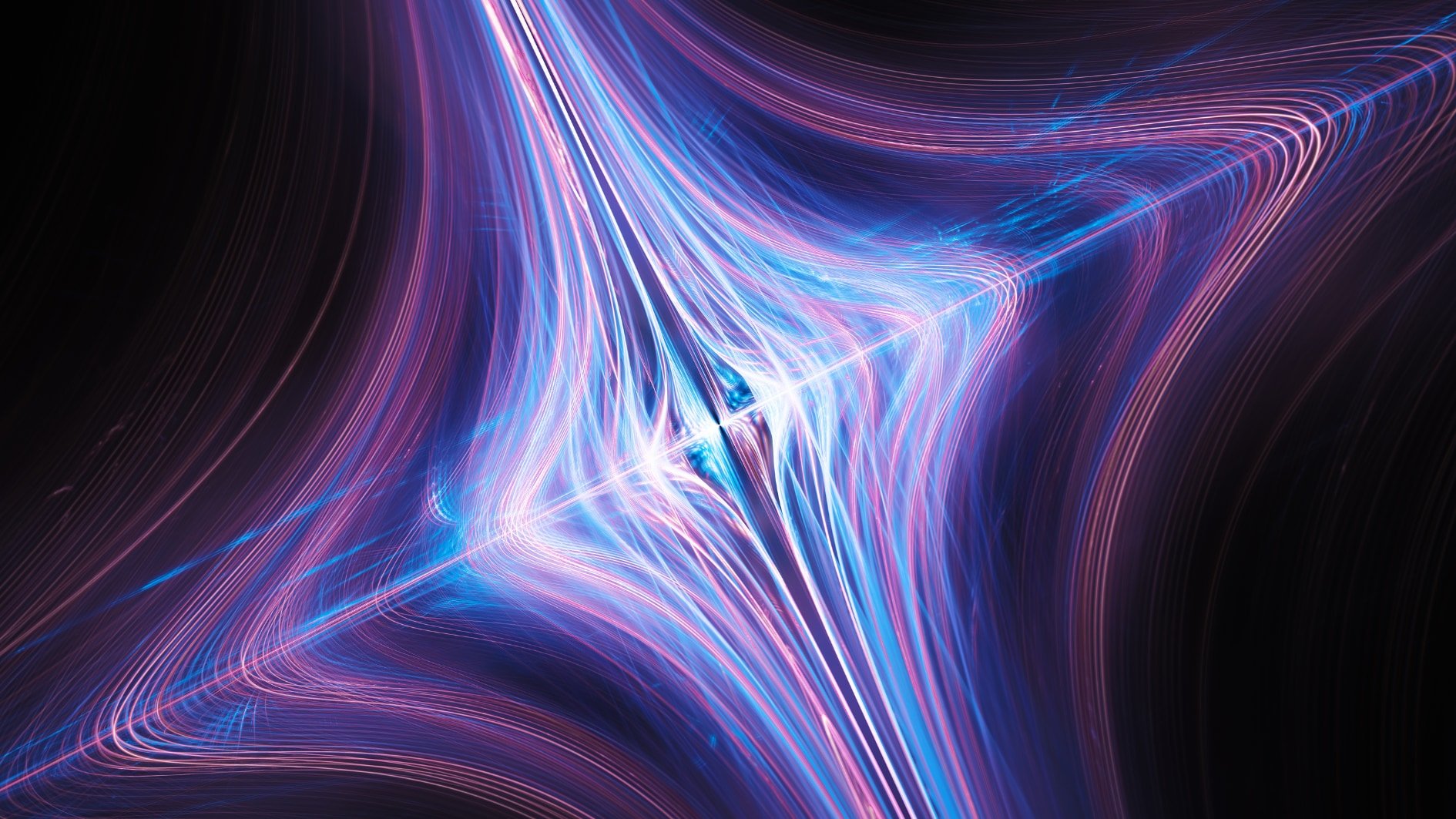



























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)














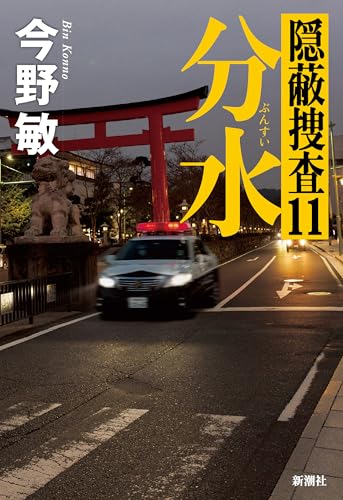



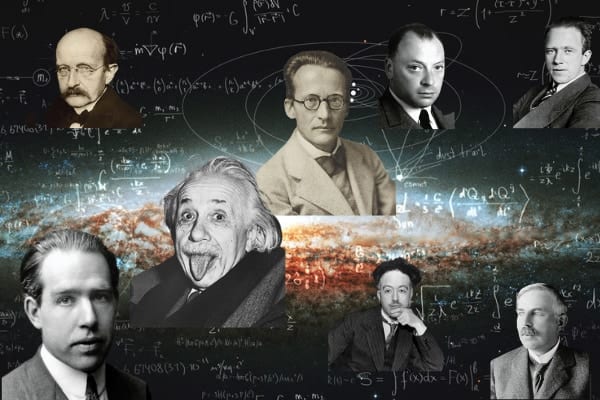


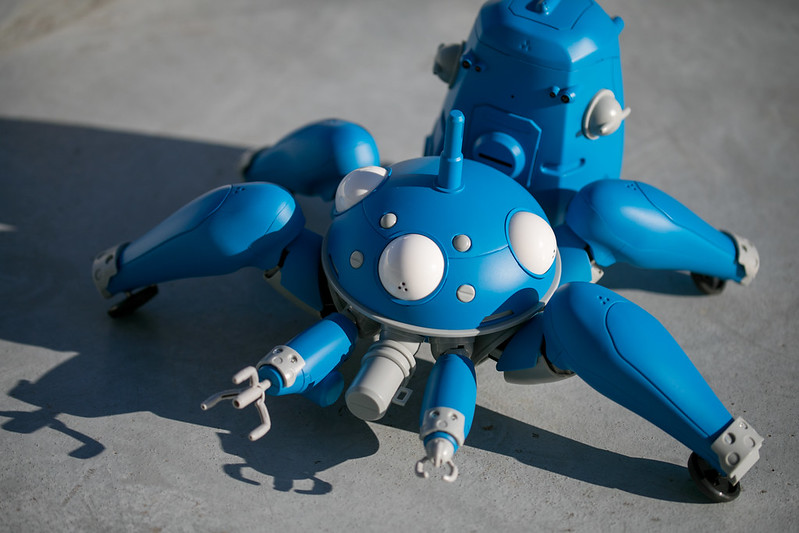






これゼノギアスの「事象変移機関ゾハル」だ
※以下長文となりますので、任意にご編集ください
元論文↓のロジックは奇妙でわかりにくいですね
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.073601
(1)Cavity optomechanical laser coolingの resonatorの機械振動(phonon、温度に相当)は、アンチストークス光子の放出でエネルギーが奪われ冷却される装置設定なので、冷却が起きるのは光子放出の瞬間のはずです。
(2-1)他方、光子放出が起きない時間的区間ではエネルギー除去が起きず冷却も行われないはずです。
(2-2)しかし、論文が確率的マスター方程式で検証した「ゼロ光子検出冷却」が有効であるならば、
光子が検出された場合(1)も検出されなかった場合(2-2)も冷却が進む事になり、冷却は光子の検出有無と無関係であるかのように見えるかもしれません。
しかし元論文の主旨は、従来手法(1)に本論文手法(2-2)を加味して更なる冷却が可能になるというストーリーとの事。
量子現象である光子放出の有無の観測が、量子系の状態をどう確定させどのような影響を与えるのか、
確率的マスター方程式による検証から一歩踏み込んだ議論が必要だと思いますが、それはきっと元論文の責任範囲ではないのでしょうね。
僭越ながらとてもトリッキーな論文だという印象が残りました
先の私のコメントの疑問点は
元論文とセットの関連論文の話題のようですね
Jack Clarke, et al. (2025-02-18) Theoretical framework for enhancing or enabling cooling of a mechanical resonator via the anti-Stokes or Stokes interaction and zero-photon detection. Phys. Rev. A 111(2),
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.023516
某所の無意識な誘導で時間を無駄にしてしまった
無とはいったい・・・うごごご!
この論文のタイトルは”Enhanced Laser Cooling … via Zero-Photon Detection” ですが
この論文の扱う冷却は
「レーザー冷却」のような物理的冷却による持続的温度低下(機械振動エネルギーの除去)の実現ではなく
一般に「ベイズ的冷却」と呼ばれる、単発測定のデータ列から定常状態より低い温度(機械振動)のデータを条件付き事後選択する量子測定理論的冷却
の話のようです。
量子測定理論は量子コンピューティングを始めとする量子現象応用分野で発展の期待される分野であり、それが物理的冷却手段としてのレーザー冷却の上に実現されるだろう事は想像に難くありませんが、
レーザー冷却の解釈で光子放出は物理的冷却、
ベイズ的冷却の解釈で光子放出は加熱、ゼロ光子放出は冷却と事後解釈されるような
明確な相違が見受けられるので、
両者を明確に区別した上で
本論文を量子測定理論やベイズ的冷却のデモンストレーションとして受け止める方がいいと思いました
つまり、まったく分かりませんでした。
観自在で色即是空、空即是色ってことなんですかね。
特に
>>レーザー光を物体に当てて散乱させることで、光がエネルギーを運び去り、結果として物体の振動(熱運動)が冷やされるしくみです。
とか、振る舞いが既知の情報を超越しすぎててめまいすら覚える始末。
>>>レーザー光を物体に当てて散乱させることで、光がエネルギーを運び去り、結果として物体の振動(熱運動)が冷やされるしくみです。
>とか、振る舞いが既知の情報を超越しすぎててめまいすら覚える始末。
それは普通にドップラー冷却と呼ばれるレーザー冷却の基本的な原理です。ネットで検索すればいくらでも情報は出てきます。簡単な論理的仕組みの話もあります。要はすでに現実世界で実現できている事象であり、これはあなたが言う「既知の情報」そのものです。この記事や引用の論文で言われているような量子力学のある意味非常識的な非直感的な振る舞いの話ではありません。
この時点で躓いていて理解できないようであればそれ以上この記事や論文については何も理解できないと思います。
この論文で使用されているレーザー冷却は
doppler coolingではなく
Raman side-band coolingです。
正確な説明をせずに、自演で頭ごなしの否定をして周りへの威嚇を試みるのは
匿名掲示板の反知性主義的言動と酷似しています。
知性をアピールしたいのであればそのような無作法な事はせず、レーザー冷却の種別を判別し解説を試みるべきでしょう
古典論的解釈と量子論的解釈の相違の話も、もっと具体的に説明すべき話に見えます。
この論文があからさまに示す、
・レーザー冷却の光子放出直前の高温状態と事後の「冷却」を
・ベイズの条件付き事後選択では「加熱」にすり替えて、光子放出が起きない低温状態を「冷却」だと言い張る論法は
一件滑稽な詭弁に見えるのですが、
その論法は量子測定の文脈(量子ジャンプや弱測定)では既に合理化され受け入れられている様子であり
その断絶を明確に示している点がこの論文の存在価値でありそれ故にPRLに掲載されたように見えます