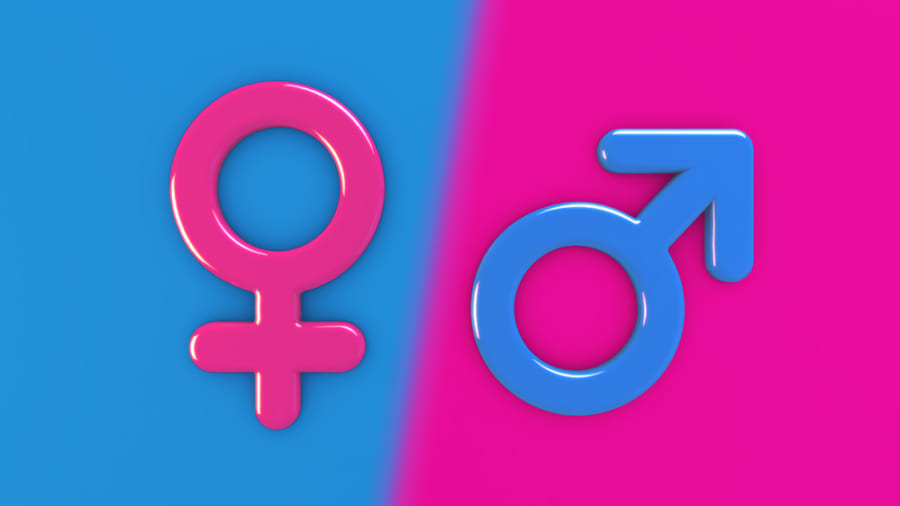「倫理 vs 実用性」――心臓移植を阻む2つの壁
心臓移植のドナーは従来、脳死ドナー(brain death donor)から得られるのが一般的でした。
脳死ドナーでは心臓は人工呼吸器などで拍動が保たれた状態で摘出されます。
しかしこれらの心停止後からの移植は時間がかかるため、移植心臓にダメージが蓄積してしまうというリスクがありました。
そこで近年2つの「末期患者の生命維持装置を停止させその後移植を行う方法」が実施されています。
1つは「体内常温灌流法(NRP)」と呼ばれる方法です。
この方法では末期患者の生命維持装置を意図的に停止させ、ドナーの心臓の停止を確認した後に、人工的に再起動させる過程が入ります。
心停止後数分、迅速に死亡判定が行われると同時に、体外循環装置を用いて心臓や臓器に血液を送ることで、臓器を健康な状態に保つことが可能です。
生命維持装置を停止させるタイミングを選ぶことで、移植のタイムラインをある程度設定することが可能になります。
(※もちろん患者の意思や家族の同意のもとに行われます)
ただこのとき、脳へと続く血管に絶対に血液が流れ込まないようにしなければなりません。
移植開始時点でドナーは既に死亡判定を受けており、処置が行われているタイミングでドナーは脳死や心停止に続く、より一般的かつ全身的な死へ向けてのプロセスを辿っています。
そこに人工的な装置で血液が脳に送り込まれれば、死への道順がキャンセルされてしまう可能性があります。
あえてわかりやすさのための極端な例を使えば、死亡判定後に脳に血液が流れ込み、医師たちが気付かぬうちに脳活動が回復してしまった場合、その状態で臓器の摘出が行われるという許容できない事態が起こり得ます。
そのためこの手法では脳に血液が行かないように厳重に脳への血管が封鎖されます。
この状態が成功すると、ドナーの脳には血液が届かないまま、心臓や他の臓器だけが移植可能な状態で維持されることになります。
ただこの方法には倫理的な負担がありました。
まずは先に述べた「脳への血流を意図的に遮断する行為自体が倫理的に問題だ」とする指摘です。
死亡判定が行われた「遺体を対象にしている」という一定のラインはあるものの、「意図的に脳へ血流を止める」という処置は、「脳に重大なダメージを与える行為」であり医学の理念の逆を行くのではないかという難しい疑問も浮かびます。
また法律上は「心停止が不可逆であること」が死亡判定の条件ですが、機械の力とはいえ心臓が再び動き出すことに対して「それは本当に死んだと言えるのか?」という指摘もありました。
さらに心臓から脳へと続く血管は毛細血管を含めて無数にあるため、主要な血管を締め付けても僅かながらに脳への血流が起こるとする意見もありました。
実際、NRP法はイギリス、スペイン、ベルギー、オーストラリアなど一部の国では許可され、実施されていますが、ドイツなど多くのヨーロッパ諸国や一部のアメリカの州では許可されていません。
NRPを許可する国は、この方法によって移植可能な臓器が増え、多くの命を救うという利益を優先しています。
一方、許可しない国は、上述の倫理的な問題を重視し、人道的見地から拒否しているのです。
(※日本では、そもそも循環死後の心臓提供が認められておらず、NRP法も現在の法律や倫理的な基準から見て受け入れられる状況にはありません。)
もう一つのアプローチは心臓用保存装置を使用します。
生命維持装置を意図的に停止させ、心臓停止を確認し死亡認定するまでは同じです。
しかしこちらの方法では心臓を体外に取り出して専用の灌流マシン(通称「心臓の箱」)に繋ぎ、移植まで心臓を拍動させながら維持する方法です。
先ほどの体内常温灌流法(NRP)が患者の体内で心臓を再起動する方法であるとしたら、こちらの方法は移植する心臓を一度患者の体内から外部に取り出し、そこで再起動させるものとなります。
ドナー体内で心臓を動かさないため倫理的負担はやや軽くなりますが、この手法を実現させるための装置が非常に高価で操作も複雑です。
また心臓を生かすと言っても体内にあったときとは状況が大きく異なるため、保存状態は決して完ぺきとはいえず、その状態で心臓の再起動を行うのはリスクを伴います。
さらにこの方法では心臓以外の臓器を同時に維持できないため、他の臓器提供にはつながりにくいという制約も指摘されています。
以上のように、体内常温灌流法(NRP)は倫理面で、心臓用保存装置は実用面でハードルがありました。
結果として、循環死ドナーから提供可能な心臓であっても活用されずに多くの患者が心臓移植を待ちながら亡くなっている状況が続いています。
このような現状を変えるには、低コストで簡便かつ倫理的に受け入れやすい方法で停止した心臓を保存・利用する技術が求められていたのです。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)