寝すぎは「原因」ではなく「症状」なのかもしれない
「たくさん眠っているのに疲れが取れない」「10時間寝ても眠い」
そんな経験がある人は少なくないかもしれません。
実は、長時間の睡眠は体に何らかの異常が起きているサインである可能性が高いと考えられています。
たとえば、うつ病や慢性的な痛み、代謝の異常など、すでに健康状態が悪化している人は、体が回復を必要としていたり、薬の副作用や症状によって自然とベッドにいる時間が増えてしまう傾向があります。
また、こうした人々は睡眠の「質」が低いことも多く、結果として「長く眠っているのに休めていない」という状態に陥ります。
これは、質の悪い睡眠を補うために“長さ”でカバーしようとしているに過ぎないのです。
さらに喫煙や肥満といった生活習慣の乱れも、睡眠の質と深く関わっています。
つまり、長時間の睡眠が健康を悪くしているのではなく、元々の不調や生活習慣が長時間睡眠を引き起こしている可能性があるのです。
このように「寝すぎ」は単なる生活習慣ではなく、体が発している警告サインである場合もあるのです。

その一方で、生まれつき遺伝的に「ロングスリーパー」の方々も存在します。
こうした人たちは元から睡眠時間が長く、ときには10時間近く眠ることで初めてすっきりと目覚め、日中も元気に活動できるという特徴があるのです。
例えば、かの天才アインシュタインもロングスリーパーだったことで知られ、一晩の10時間以上眠ることが普通でした。
問題なのは、元々は7〜8時間睡眠だった人が急に9〜10時間睡眠になった場合です。
こうした人たちは体になんらかの異変が起きている可能性があるので、注意が必要であり、医師の診断を受けた方がいいかもしれません。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)





















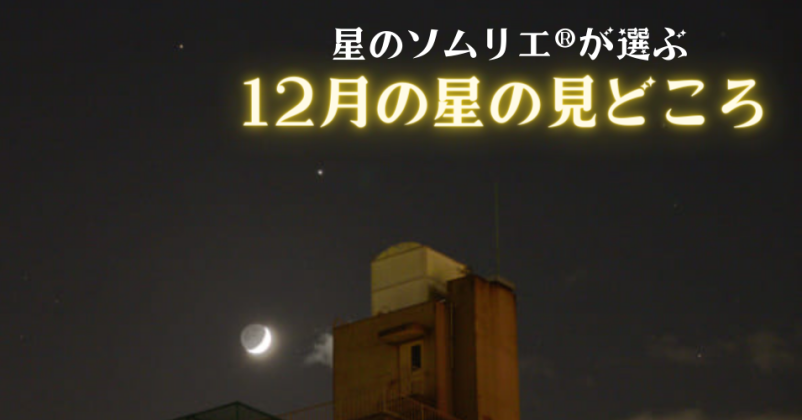






長くても駄目、短くても駄目、しかもその基準はおそらくコロコロ変わる。
合わせてるとそっちのほうがストレスになって短命になりそうな気配…。