出会いの場はスマホとカフェへ?都市に起きた「社交の移動」
それでは、なぜこのような変化が起きたのでしょうか。
研究者たちは、いくつかの現代的要因が背景にあると指摘しています。
第一に挙げられるのが、スマートフォンの普及です。
かつては「街でたまたま友人に会う」「誰かとばったり話し込む」といった即興的な交流が日常的でした。
しかし現代では、誰かに会う前にまずメッセージを送り、場所と時間をきっちり決めて行動する、あるいは今日1日の予定をスマホで決めておいて、そのスケジュール通りに動くことが一般的です。
MITの研究者ラッティ氏は「ホワイトの時代(70〜80年代)、人々は周囲の人をよく見ていました。
公共空間は出会いの場であり、会話が自然に生まれる場所だったのです。今はまずスマホで連絡を取り、その後に空間を利用する、という順番に変わっています」と述べています。
もうひとつの変化は、コーヒーショップの存在です。
1980年当時、今のように大手チェーンのカフェが街の至る所にあるという光景はまだ存在していませんでした。
しかし今では、誰かと話したければ静かで空調の効いた店内に入るという行動が一般的です。
今回の論文では「カフェなど屋内空間の増加が、屋外での立ち話やグループ交流の減少につながっている可能性がある」と述べられており、私たちの社交の舞台が“屋外の広場”から“エアコン付きの私的空間”へと移行したことが示唆されています。

都市が変化するにつれて、私たちの行動様式も変化します。
便利さや効率を求めるうちに、私たちは歩くスピードを上げ、立ち止まることをやめてしまったのかもしれません。
けれど、都市における公共空間の役割は、単なる「通り道」ではありません。
偶然の出会いや、小さな会話、風を感じるひととき――それらが、人と都市の関係性を豊かにしてきたのです。
チームは今後、ヨーロッパの40都市での映像解析に乗り出す予定です。
人と空間の関係が、国や文化によってどう異なるのかを明らかにするためです。
立ち止まること、予定を決めずにぶらぶら散策することには意味があります。
あてどもなく都会をぶらつき、周囲の人をよく観察して、街のどこかでふと立ち止まってみる。
そこに思いがけない出会いが待っているかもしれません。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




















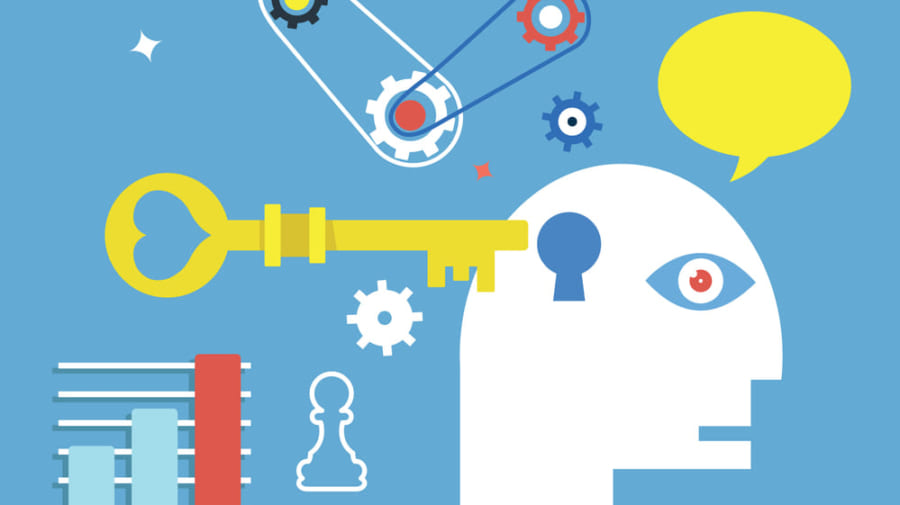







そうは言うがな、大佐。
のんびり立ち止まるには今の街は暑すぎないか?
木陰や日陰、できれば街の道そのものを屋根などで覆って空調をしてもいいくらいだと思うぞ。
季節に影響されすぎ。温暖化で夏が暑くなってるなら冬は暖かくなってるんだからプラマイゼロでしょ。
これはアメリカの話だからこれで良いけど、日本でなら岡檀「生き心地の良い町」とその続編の森川すいめい「その島のひとたちは、ひとの話をきかない」によれば「ベンチや縁側が無くなった」事が人々が孤立化している一因です。ゴミ箱が無くなった事もそうでしょう。ゴミ箱もベンチもない公園では誰もコンビニ弁当なんて食べないから面識無い人同士の交流も生まれない。
温暖化の進んだこの暑さじゃ外で会話なんてしてること自体が危険だからな…