43年の軌跡と発見された「長寿の秘密」とは?
一般多岐なトダテグモの寿命は5~20年と言われています。
しかしナンバー16は研究チームの想像をはるかに超えて生き続け、メイン氏が始めたプロジェクトは40年以上も続くことになりました。
メイン氏は80代後半までこの仕事を続けたものの、健康状態の悪化により、調査を他のメンバーに引き継いでいます。
ところがそんなプロジェクトにも幕が下ります。
2016年、調査チームはナンバー16の巣穴の異変に気づきます。ナンバー16が姿を消していたのです。
巣穴の蓋に小さな穴が開いており、研究チームは、これが寄生バチによるものだと推測しました。
寄生バチは寄主の体に卵を産みつけ、生まれた幼虫は寄主の中からその体を食べて成長していくことで知られています。
つまり、ナンバー16の死因は老衰ではなく、この寄生バチに刺されたことだったと考えられます。
それでも43年間も生き抜いた野生のクモの記録は世界でも例がありません。
従来のギネス記録は、飼育下のタランチュラが28歳まで生きたというものでしたが、自然環境下でこれほど長寿のクモが観察されたのは驚くべきことです。
なぜナンバー16はこれほど長生きできたのでしょうか?
その理由のひとつは「巣穴での引きこもり生活」にあります。
Gaius villosusのメスは、自分で作った頑丈な巣穴の中でじっと獲物を待ち、必要最小限しか外に出ません。
巣穴の壁や蓋は自らの糸で固められ、外敵や乾燥から身を守るのに役立ちます。
巣穴の作り直しや引っ越しには大きな労力とリスクが伴うため、できる限り同じ場所にとどまり続けるのです。
調査チームは、「環境負荷の低い生活が、ナンバー16の長寿の秘訣だった」と推察しています。
そして、「短距離しか移動しない在来種のライフスタイルは、人類や持続可能な社会への教訓となる」とも続けています。
つまり「必要なものだけを得て、無理な拡大をせず、地道に生きることが、豊かに長く生きる秘訣」といえるでしょう。
ナンバー16の物語は、身近な小さな命にもサバイバルドラマがあること、そして科学の地道な観察がどれほど貴重な発見につながるかを教えてくれます。

































![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



















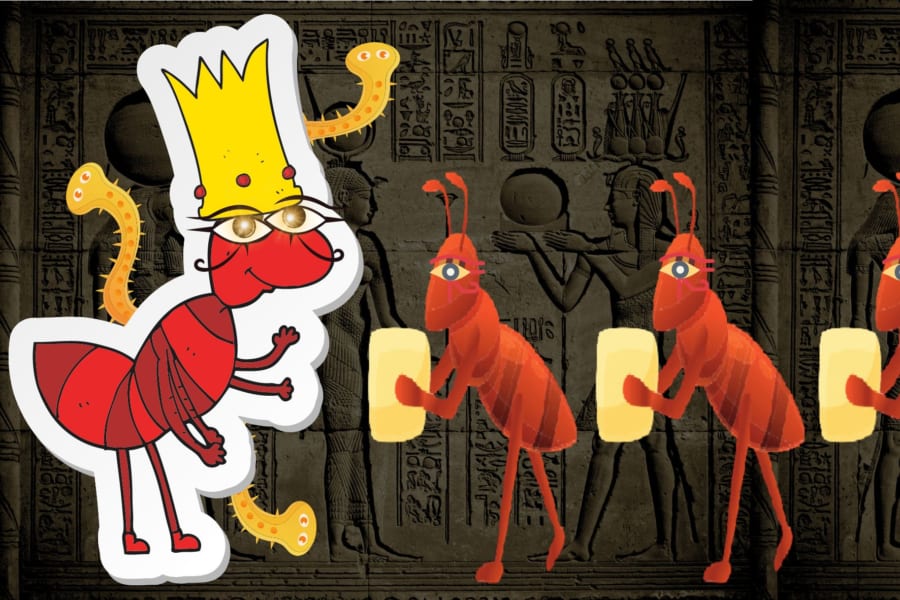
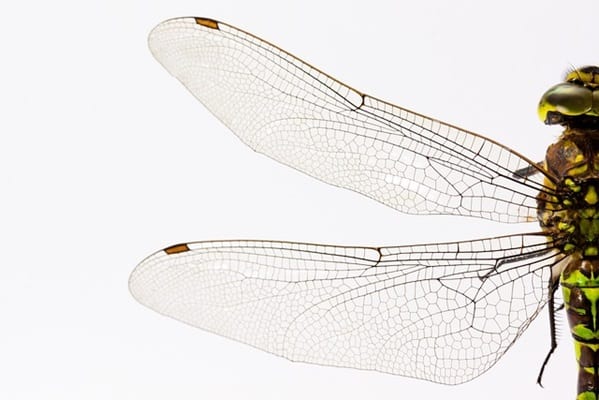

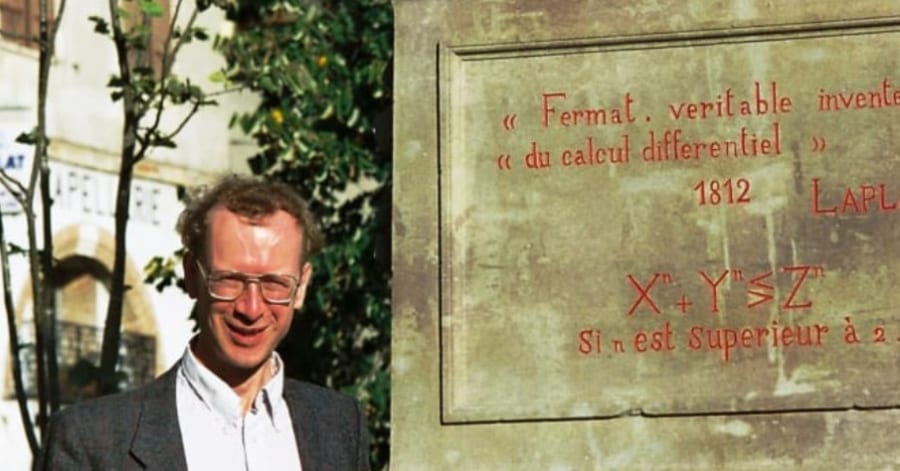






クモでも「引きこもり」が長寿の最適解なんですね
人間も長生きしたければ、なるべく引きこもりの努力をしないとダメですね