サメに遊び心があるとしたらそれは何を意味するのか?

今回の発見をひとことで言えば、「サメにも“遊び様の行動”があった」ということです。
この一文には、海の捕食者に対する私たちの固定観念を大きく揺さぶる力があります。
これまでサメは、獲物を追い、食べ、生きるためだけに泳ぎ続ける「本能の化身」のように思われてきました。
しかし、満腹になったあとでおもちゃに向かい、輪っかをくぐったり、鼻でつついたりする姿は、まるで別の生き物のようでした。
サメも状況に応じて行動を変える柔軟さと、未知の刺激に反応する知的好奇心を持っている──そう考えざるを得ません。
今回観察された行動は、サメが環境と「かかわろうとする力(認知的関与)」を示しているように思えます。
単に反射的に動くのではなく、「面白そうだから近づく」という意識の芽を感じさせるのです。
中でもカリフォルニアドチザメたちの活発さは象徴的でした。
おもちゃの輪っかを「自分のもの」と言わんばかりにくわえて離さず、何度も輪っかに戻っていく。
その動きは、まるで子どもが好きな遊具を独り占めしているようでした。
研究チームはこの観察から、「サメにも環境から楽しみを見つける力がある」と感じ取っています。
それは知性の証というより、「生きる力の余白」を見せてくれたようでもあります。
コラム:なぜ遊びは高度なのか?
動物の遊びをよく観察すると、それが単なる気まぐれではないことに気づきます。遊びとは、生き物が生きるための能力を安全な環境で試し、練り直し、洗練させる「行動の実験室」なのです。たとえば、子どものライオンがじゃれ合いながら噛みつきの力加減を学び、カラスが枝を落として風の流れを確かめるように、遊びは行動のバリエーションを増やす訓練になります。狩りや逃げる練習であると同時に、「何が起きても対応できる柔軟さ」を鍛える行動なのです。しかも遊びには決まったゴールがありません。動物たちは途中でやめたり、ルールを変えたり、別の動きを試したりします。この「自由度の高さ」こそが、遊びを高度な行動にしている理由です。目的を決め、自分の行動を調整し、変化に応じて戦略を変える――それはすでに認知の働きです。今回の研究で観察されたサメたちも、まさにその例でした。彼らは単に輪っかにぶつかっていたわけではありません。鼻先でつつき、かじり、くぐり抜けるなど、明確な動きを繰り返していました。そこには「どう反応すれば面白いか」を自分で探るような意図が見えます。つまり遊びとは、外から与えられた刺激にただ反応するのではなく、自分の行動を使って環境を“実験”する行為です。動物が遊ぶとき、脳は新しいパターンを作り、古いルールを壊して再構築しています。そこには学習・記憶・判断・予測といった、知性の根っこがすべて動いているのです。だからこそ、遊びは高度です。遊ぶことができるというのは、ただ生きているだけではなく、「生き方そのものをデザインできる」力を持っているということなのです。
今回の研究成果は、水族館や水産施設で飼育されるサメの福祉改善という面でも大きな意味があります。
「福祉改善」とは、動物がより快適に暮らせるように工夫することです。
たとえば動物園ではトラに池や木登り用の台を用意したり、サルには遊具を与えたりして、退屈やストレスを減らしています。
水族館でも同じように、サメが意味もなくぐるぐる泳ぎ回るようなストレス行動を防ぐためには、適度な刺激や遊び道具を与えることが重要です。
今回の研究では、どのようなタイミングで、どんなおもちゃを使えばサメがより活発になるかが明確になりました。
水族館でエサを与える時間が決まっているなら、その直後に黄色やオレンジなどの目立つおもちゃを入れるとよいでしょう。
そうすれば、満腹になったサメが自然な動きを見せやすくなり、観察にも適した展示が作れます。
こうした工夫は来館者にとっても新鮮な体験を生みます。
「サメがおもちゃで遊ぶ」という光景は、サメへの印象を「恐ろしい生き物」から「身近で知的な存在」へ変えていくきっかけになるかもしれません。
もちろん、この研究にも限界があります。
観察された4種類のサメやエイのうち、明確に輪っかで遊ぶ行動を示したのはカリフォルニアドチザメだけでした。
夜行性のツノザメやカリフォルニアネコザメは、昼間の観察ではあまり関心を示しませんでした。
研究チームは、観察時間帯の違いが影響した可能性を指摘しています。
夜に観察すれば、また違った反応を見せるかもしれません。
また、今回使用したおもちゃは輪っかという単純な形状のものでしたが、形や大きさを変えればサメの反応も変わる可能性があります。
さらに、より長期間の観察を行えば「飽き」が生じることも考えられます。
そのため、研究チームは「おもちゃを定期的に入れ替えたり、配置を変えたりする工夫」が必要だと述べています。
こうした限界はありますが、それでも今回の研究はサメの行動研究に新しい視点をもたらしました。
理論的な知見だけでなく、実際にサメをより自然で健全に飼育するための実用的なヒントを示した点に大きな価値があります。
使われた輪っかは、私たちにもなじみのある市販のプール用おもちゃに近いものでした。
身近な道具でサメの生活を豊かにできるという点で、とても効率的な福祉向上の方法といえるでしょう。
今後の研究では、今回あまり反応を示さなかった夜行性のサメを夜間に観察したり、野生のサメが自然の中で同様の行動を見せるかを確かめることが次の課題になります。











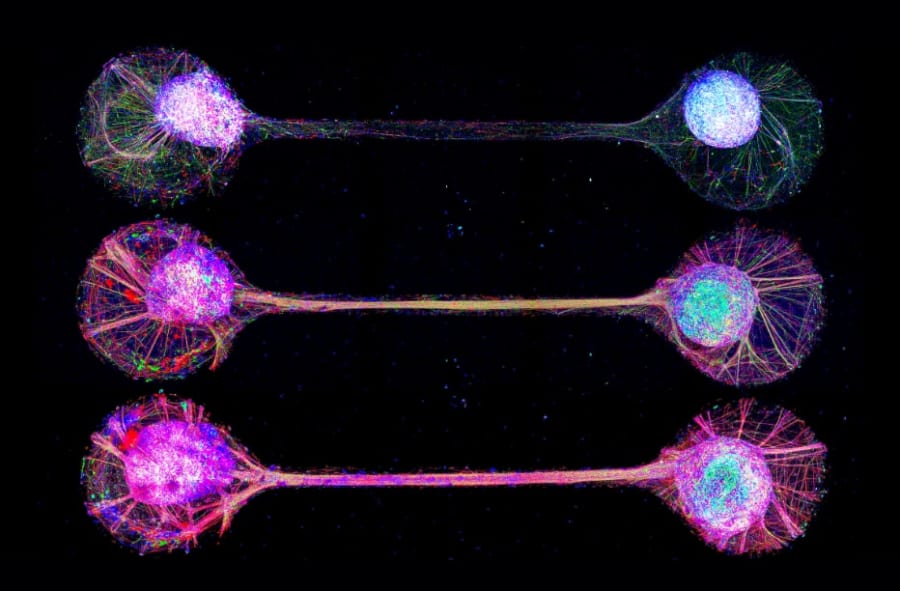




















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)















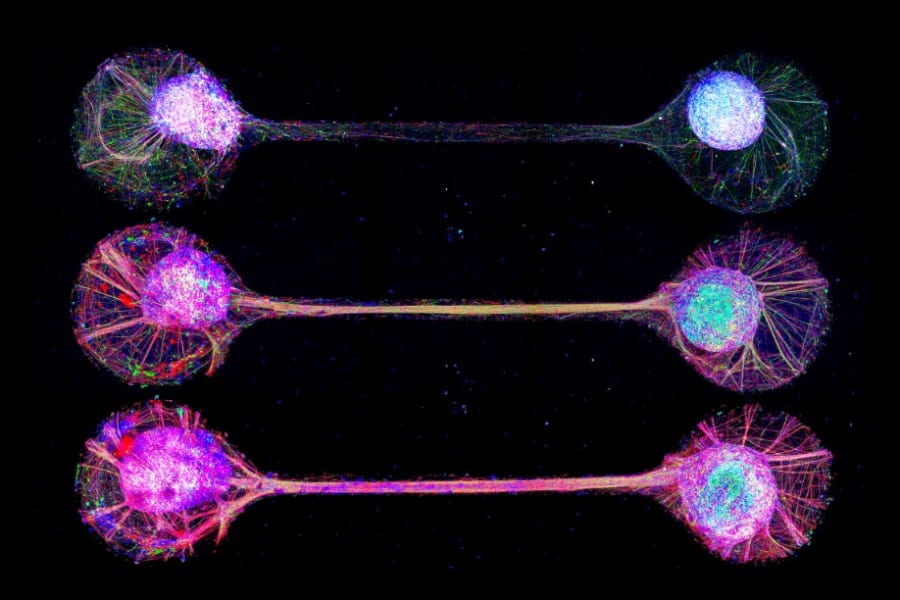





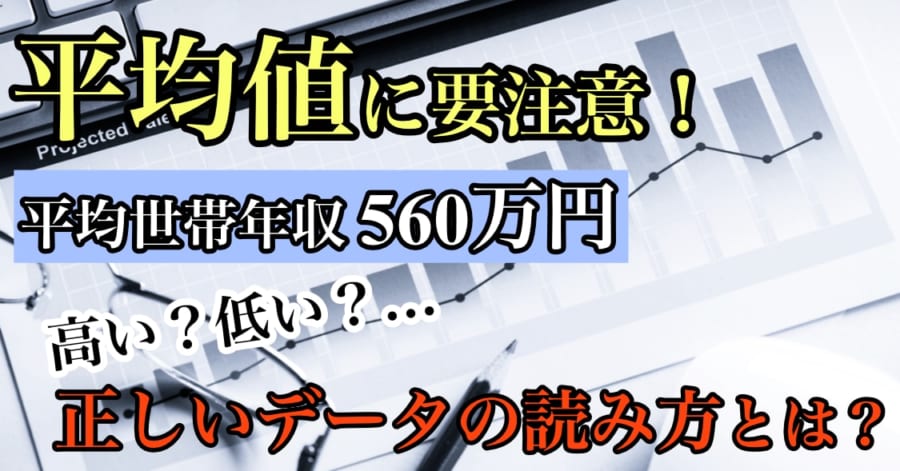






細菌とかウイルスにも遊びの概念があるかもですね。