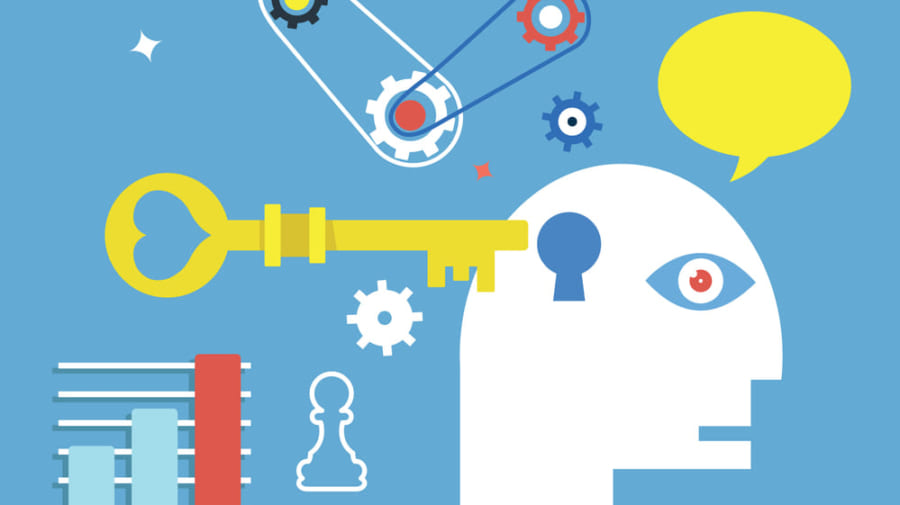なぜイモガイの毒インスリンは速効性があるのか?

これはイモガイが魚を捕食する様子です。
ちょっとショッキングですが、そろ~りと伸ばされた触手が触れただけで魚はすぐ抵抗する力を失いぐったりしたまま丸呑みにされてしまいました。
ここでイモガイが触手の先から魚に注入しているのがインスリンです。
イモガイは一瞬のうちに毒インスリンを注入していて、小魚は低血糖ショックを起こして気絶しているのです。
しかし、現在人間が医療で用いるインスリンには、ここまでの即効性はありません。
なぜイモガイのインスリンはこれほど即効性が高いのでしょうか?
その秘密を知るには、まず、インスリンの仕組みを理解しなければなりません。
インスリンは、血糖値を下げる働きをするホルモンで、すい臓で生産されます。
しかし、糖尿病になると、十分なインスリンが作れなかったり、効果が発揮されなくなるため、血中を流れる糖分が増えてしまいます。
そこで、外部注射により足りないインスリンを補います。
重要なのは、ここからです。
インスリンが体内で効果を発揮するには、分子が1つの状態(単量体といいます)にならなければなりません。
しかし、注射用のインスリン薬は、6つの分子がひとかたまり(6量体)になっています。
6分子の状態だとインスリン分子が安定するからです。
これを体内に注入すると、細胞間にある液体でだんだん薄くなり、6量体から2量体に、そして最終的に単量体へと分解されます。
こうして血管の中に入り込めるようになり、全身の1つ1つの細胞までインスリンが届いて、効果を発揮し、血糖値を下げてくれるのです。

問題は、インスリン分子が集まった状態から分離するまでに1時間ほどかかることです。
この「遅延」のせいで、すぐさま血流に移行できず、たとえば、食後の急速な血糖上昇などに対応できなかったりします。
これは、インスリン注射の大きな課題でした。
ところが、本研究チームのヘレナ・サファヴィ(Helena Safavi)氏は、ユタ大学のポスドク研究員をしていた際、アンボイナガイ(Conus geographus)というイモガイの毒インスリンが「分子のクラスターを作らない」ことを発見したのです。
詳しく調べてみると、毒インスリンは6つの分子ではなく、1分子で安定した状態にありました。
つまり、イモガイは医療で使われるものと異なりいつ使っても、瞬時に効き目を発揮し、魚を気絶させられるインスリンを使っていたということです。
研究チームは、この分子の特徴を組み込めば、ヒトインスリンに「速効性」を持たせられるのではないかと考えました。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)