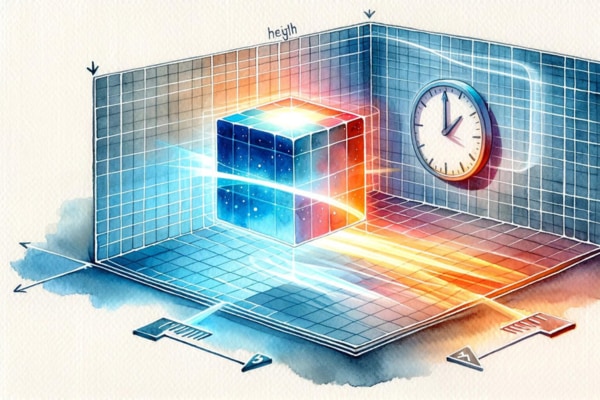銀と銅の攻撃力はどこまで? データが示す抗菌効果
実は、銀と銅は古くから衛生管理に使われてきました。
銀食器が歴史的に重宝されたのも、食品の腐敗を遅らせる力が期待されたからではないかといわれています。
それぞれの抗菌メカニズムは次のように考えられています。
銀イオン(Ag⁺)の原理
湿度のある環境で銀がイオン化すると、微生物やウイルスに必要なタンパク質や酵素と結合し、機能を失わせると考えられています。
特にタンパク質の中でも、硫黄(-SH)などを含む部分と銀イオンが結合すると、酵素が活動できなくなることが判明しています。
細胞膜に取り込まれた銀イオンは、微生物が呼吸や栄養のやり取りに必要な酵素を停止させ、増殖や生存に大きなダメージを与えます。
比較的少ない濃度でも殺菌力を示す一方、人間にとっての毒性リスクが小さいことが、長く利用されてきた理由とされています。
銅イオン(Cu²⁺)の原理
銅がイオン化すると、菌やウイルスの膜を酸化し、ダメージを与えます。
また、細胞内部で活性酸素(酸化力が強く、細胞構造を破壊しやすい酸素分子)を発生させるため、DNAやタンパク質を損傷させる効果も期待されています。
また、銅イオンには酵素反応を妨げる、細胞膜に穴を開けるなど、複数の段階で微生物を死滅に導くという報告もあります。

こうした銀や銅を放出する塗料をドアノブに加工し、1年間培養試験を行った事例があります。
結果は、培養陽性率(菌が培地で増殖したサンプルの割合)が2.8%程度にとどまり、加工していないドアノブでは約90%に達しました。
数値の大きな違いから、銀や銅に一定の抑制効果があることが示されています。
ただし、塗膜の剥がれや汚れがたまると、イオンが十分に放出されにくくなるため効果が落ちる可能性があります。
また、極端に使いすぎることで耐性を持つ菌が出現するリスクも指摘されているので、定期的なメンテナンスや使用上の注意が必要です。




























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)