種は「ひと組」ではつくれない――多様性と進化の仕組み
生命は何らかの完成体が単体で生まれたのではなく、化学反応を繰り返す分子の群体として生じたというのが妥当な推論です。
では、生命が誕生したとして、それが種として繁栄していくにはどうすればよいのでしょうか。
まず問題になるのが、先程から議論してきた「遺伝的多様性」という要素です。
ある程度の数が存在したとしても、出発点が極端に限られた個体だったとしたら、当然ながら遺伝的なバリエーションはほとんどありません。
その結果、ハプスブルク家のような問題が現れます。集団の個体数が一時的に大幅に減少した後に再び増加した際に、遺伝的多様性が失われる現象を「ボトルネック効果」と呼びます。
実際に、絶滅危惧種や孤立した島の動物では、この効果によって遺伝的多様性が著しく低下し、将来の生存に深刻な影響を及ぼす例が数多く報告されています。
しかし、これは交配によって親から子という限られた遺伝子伝播の方法しかない場合に生じる問題です。では初期の生命はどうしていたのでしょう?
わかりやすいのは、細菌などの原始的な生物が持つ「水平伝播」と呼ばれる仕組みです。
これは、親から子へ遺伝子を伝えるだけでなく、仲間どうしで遺伝子の情報を直接やりとりする方法です。
たとえばある細菌が抗生物質に対する耐性を手に入れると、その情報を別の細菌に“コピー”して渡すことができます。この仕組みによって、環境の変化に対する適応力が高まり、進化が加速されるわけです。
ただし、私たち人間のような複雑な生き物には、このような遺伝子の“横のやりとり”は基本的にありません。
(血清療法は、生物進化における「水平伝播」のイメージにかなり近い医学的手法ですが、共有しているのは遺伝子そのものではなく“成果物”である抗体です。そのため進化の視点では一時的な効果しかありません)
そのため、私たち人間のような複雑な生命が健全な進化や繁栄を目指すには、最初の段階からある程度の個体数と遺伝的多様性が必要になるのです。
進化は、個ではなく“集まり”から生まれた
神話のように「たった二人からすべてが始まった」という考え方は、イメージとしては分かりやすく面白いですが、実際、生命や種が繁栄するためには多くの個体による協力と変化の積み重ねが不可欠です。
生命の起源は、分子のレベルから始まり、それらが相互に支え合いながらネットワークを築いたことで可能になりました。
そしてその後の進化は、膨大な数の個体と遺伝子のやりとりのなかで起こったものです。だからこそ、もし人類がほぼ絶滅し、たった一組の男女しか残らなかったとしたら、そこから再び人類を復活させるのは、現実的には非常に難しい――というより、ほぼ不可能だと考えられます。
SF作品の中には、世界の滅亡や他惑星への移住などで、生き残った数人の人々がここから人類を復活させていくぞ、というエンディングを希望に満ちて描くことがありますが、生物学的にはそのシチュエーションに希望はまったくありません。
地球にこれほど多様な生命が存在しているのは、最初から“ひとり”で生きていたわけではなく、地球の長い歴史を通して多くの存在がつながり合っていたからこそ。
生命とは、最初から「個」の物語ではなく、「集まり」から始まったものなのです。
「アダムとイヴのように一組の男女から種が生まれるのか?」という問いは、人によっては今更バカバカしい議論だ、と感じるかもしれません。
しかし生命とは何か、どうやって続いてきたのかを考えるための大事な入口にもなりえます。
昔、この問題に疑問を抱いた人たちがいたこと。ダーウィンのように、自分の身の回りの問題から出発して科学的な探究へと進んだ人がいたこと、そしてそれを理論で支える研究が続いたことで、私たちは今、「なぜ一組の男女からでは人類を復活できないのか」をはっきりと説明することができます。
それもまた、人類が歴史の中で続けてきた研究の成果です。
神話は世界を理解しようとした人間の最初の試みといえるでしょう。そしてそこに生まれた問いに、科学がどう応えてきたかを見ることは、科学を学ぶうえでもとても面白いことなのです。




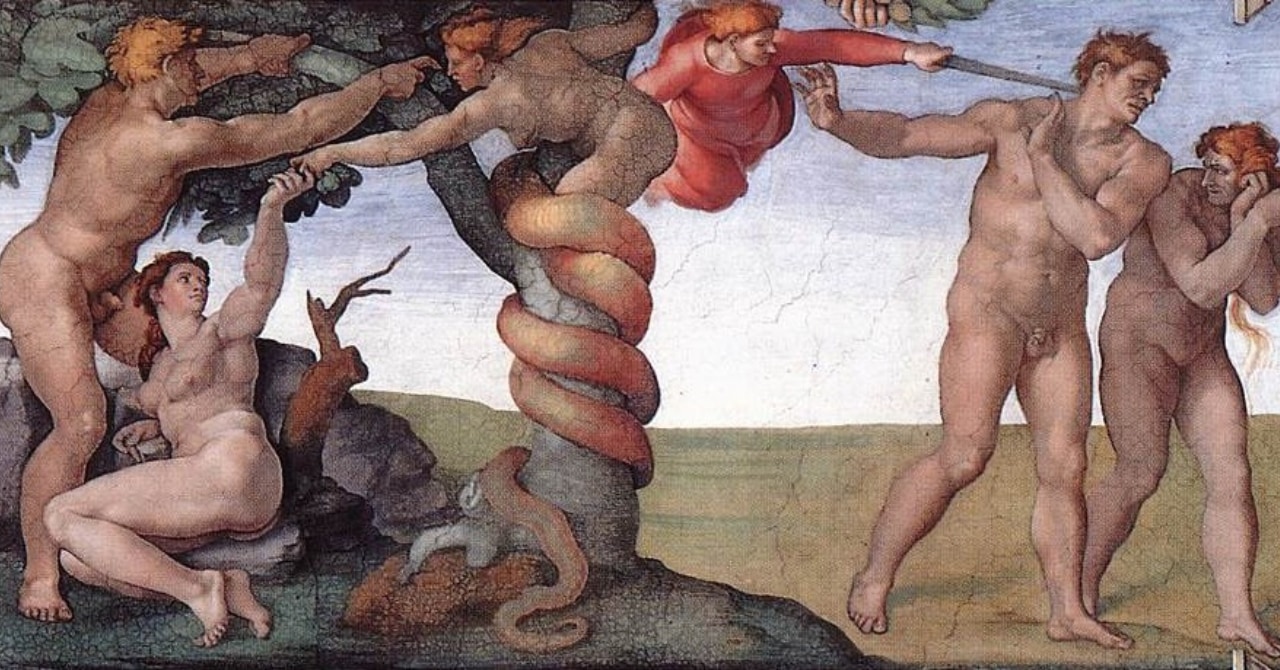


























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




















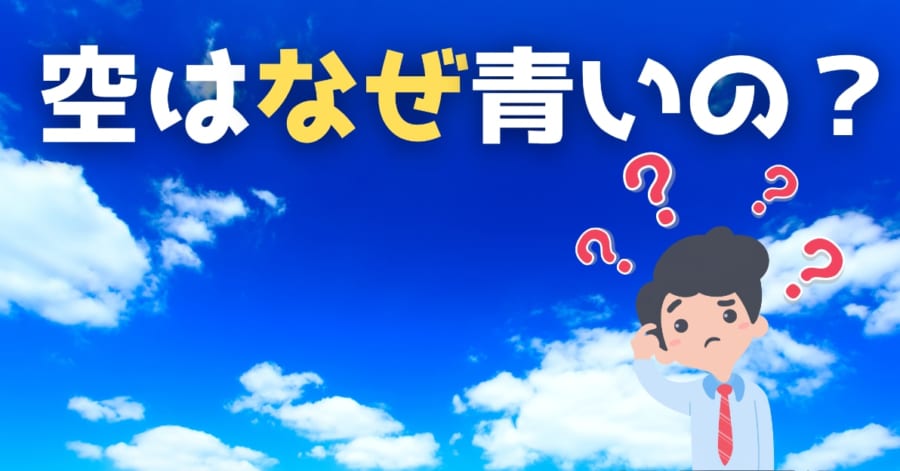







一組の男女からスタートしても人類は繫栄できる可能性はある。
一組の男女が子供を産める大人になるまで死んでないのなら
少なくとも優性遺伝の大人になるまでに死ぬような致命的な遺伝子は存在していない。
致命的な遺伝子がお互い同じ遺伝子座にヘテロで存在する数に対してそれ以上に子供をたくさん産めば繁栄は出来る。
それを何億年も繰り返せばそのころには突然変異と自然選択の繰り返しで遺伝子プールは多様性が増して環境にあった遺伝子が多くなるだろう。
賛成。
近親者の子孫に遺伝子異常が多い理由は、遺伝子自身からの多様性の発生ではないのか?
そもそも遺伝子は全ての子孫が均等に長生きするなんて考えていない。
遺伝子が同じじゃダメだから変化しなきゃって頑張った結果がまとめて劣勢だと呼ばれているだけ。
病弱、発育不良は当たり前。とにかく変化が先。不良品は淘汰されるのが当たり前。が遺伝子の考え方。
不良品まで大事に育てるのは人間の倫理の考え方。長男大事も人間の考え方。
遺伝子の近親種での生存理論と多様性獲得とは永久に合致しない。
サルが突然変異を起こしていきなりヒトが二人現れた訳じゃあるまいし、あんまり掘り下げる意味が無い話に見えた。ウマとロバが交尾してラバが作られるように、類人猿も初めは近縁のヒト以外の種と多様性を与え合っていただろうし、サピエンスもネアンデルタールヤデニソワ等と多様性を持ち合っていて、アダムイブなり世界中のそりと類似した人類創世神話は他にもいた筈のヒトを選民思想などの集団エゴよって都合よく排除し部分的に切り取っている(捜索している)と言える。俺が普段から思っている事もこの記事の「集団から始まった」と同じ。
他にもよくナマコとかウニとかが「最初にこれを食った奴は何考えてたんだ」みたいに言われるけど、人が誕生してから食い始めた訳じゃない。サルの頃から食ってたものはヒトになっても抵抗無かっただろうし、霊長類は食ってなくても他の動物が食ってるならヒトも食ってみようってなる。
近親相姦はロマン
ただしリアルは勘弁
最初にアフリカを出た人類の人数が数百人とか言われてるので
その位なら復活出来るかな?
仮定条件として、
・1人の女性が産める人数を10人
・遺伝的欠陥で4割が成人できない
・2割は遺伝的欠陥以外で亡くなる
・生まれる男女比は1:1
とすると、
第一世代 男女1:1
第二世代 男女児:5:5→成人2:2
第三世代 男女児:10:10→成人4:4
第四世代 、、、
全然増えないね。
仮定条件が厳しすぎるかな。それともこんなもん?