女性より少ないのに、なぜ男性は命を落としやすいのか?
調査の結果、患者全体のうち83%は女性でした。しかし注目すべきは死亡率です。女性の死亡率が5.5%だったのに対し、男性では11.2%と、実に2倍以上だったのです。
さらに、患者の多くが心不全(35.9%)や心房細動(20.7%)、心停止(3.4%)、脳卒中(5.3%)といった深刻な合併症を起こしており、病気自体の危険性が非常に高いこともわかりました。
なぜ、発症数が少ないはずの男性のほうが、危険な症状に発展し命を落としやすいのでしょうか?
研究チームはその理由をいくつか挙げています。
まず、男性は「身体的ストレス」が引き金となる場合も多く、重症化しやすい傾向があります。たとえば、手術や感染症、大けがなどがきっかけとなる場合が多く、発症時点ですでに危険な状態になっている可能性があるのです。
また、感情的なストレスに対しては「自分は大丈夫」と我慢し、医療機関を受診するのが遅れがちである点も影響していると見られています。そのため、診断時にはすでに重篤な状態になっていることが少なくないのです。
さらに、女性ホルモンの一種であるエストロゲン(Estrogen)には、心臓をストレスから守る働きがあるとも言われており、こうした生理的な違いも死亡率の差に関わっている可能性があります。

研究期間の5年間を通じて、死亡率や合併症の発生率はほとんど改善せず、むしろ悪化している項目もありました。つまり、医療の進歩があってもなお、この病気は命を脅かす存在であり続けているのです。
この研究は、「男性は感情的・身体的ストレスに対して過小評価されやすく、その結果として重篤化しやすい」という重要な警鐘を鳴らしています。
もし、身近な男性が大きなショックを受けたあと、胸の痛みや息苦しさを訴えていたら、それは「心の問題」ではなく「心臓の病気」かもしれません。
ブロークンハート症候群は、一見すると精神的な問題のように見えても、実際には命にかかわる心臓の疾患です。ストレスは、性別に関係なく心と体の両方に影響を及ぼしますが、特に男性の心臓には「思ったよりも大きな負担」がかかっている可能性があります。
愛する人を失った悲しみで、心が折れるだけでは済まされない。それは、文字通り「心臓が壊れる」ことにつながるのです。
どうか、あなた自身も、あなたの大切な人も、「強くあらねば」と思いすぎず、必要なときには医療の助けを借りてください。それが、命を守ることにつながるのです。












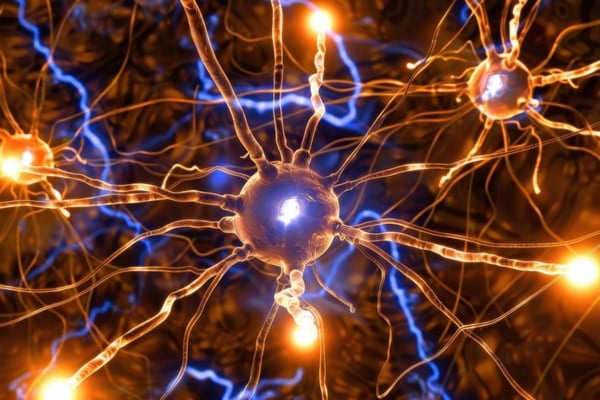
















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)















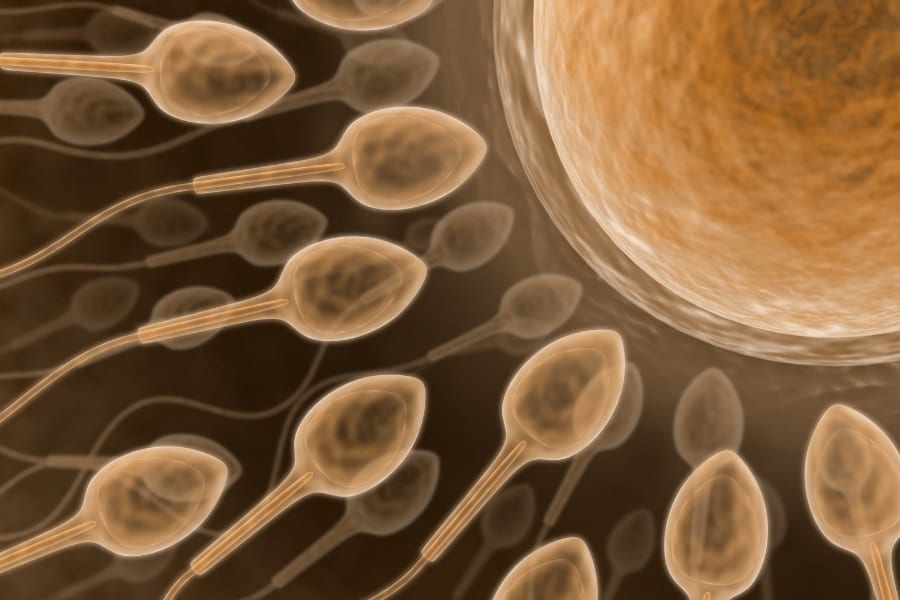


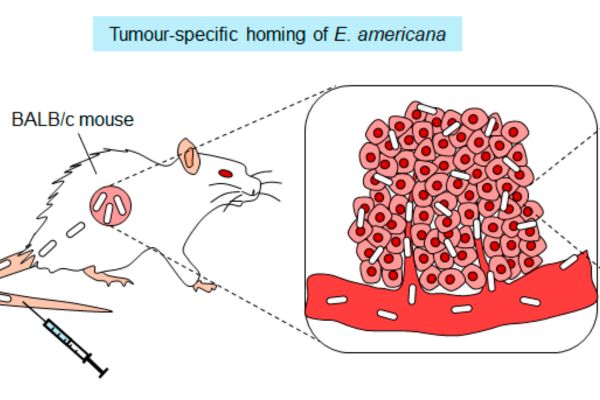

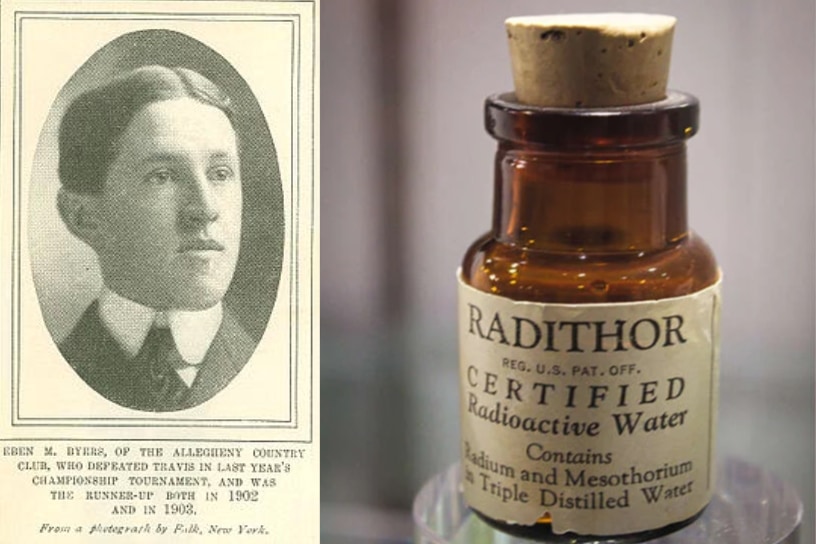







女は男に「失恋したくらいでめそめそして情けない」とストンピングを浴びせる事がある。男は共感力が低く他者と繋がる能力が弱いので一度友達や交際相手を失うとまた別の繋がりを作る事が難しいし、繋がる相手の数も少ないから相手一人当たりに温もりを依存する度合いも大きく、一人失った時のダメージが大きい。そして他者と繋がろうとする事は甘えだとか弱さだという社会ジェンダーが男の弱点を抉ってもいる。男女がマラソンしてて女は給水所にある水を気軽に手に取れるし黙っててもその性資本の大きさによって大勢から水の入ったコップを差し出されるが、男は誰からも水を差し出されないし自ら水に手を伸ばす事は自他からタブーとされているような違いがあるのを女は理解出来ない。女はセロトニンが男の2/3しかなくてストレスを受け易いのでそれをこまめに癒す事にも長けている、給水所があったら必ず水を飲むのが当たりま前になっているけど、男はストレスを受けにくい代わりに癒しを補給したら負けルールがあるために我慢大会になって自殺し合うか他者を殺す事で癒しの代用にする。その一形態が妻子へのDVで、虐待された男児はそれを次世代にも持ち越す。ではなぜ男はやせ我慢するのかというと一つは女が強い男を求めるから、もう一つは人類学的には国民性。日本は権威主義直系家族社会で、横のつながりが権威者による縦の力で分断された孤独社会なので、特にやせ我慢を自他に強いる傾向が強く、舞田敏彦「誰にも悩みを相談できない日本の子供たち」記事のグラフでは日本男性が他国と比べて極端に孤立しているのが分かる。韓国ドイツもこのタイプの社会だけど日本男性は両国に比べても極端に孤立している。ここ10年くらいで各国社会の男女分断が進んでいるけどそれが顕著になるのもこの権威主義直系家族社会。その社会の元凶は家庭の権威者である親のエゴ。