性別適合手術をするとメンタルリスクが増加する傾向がある
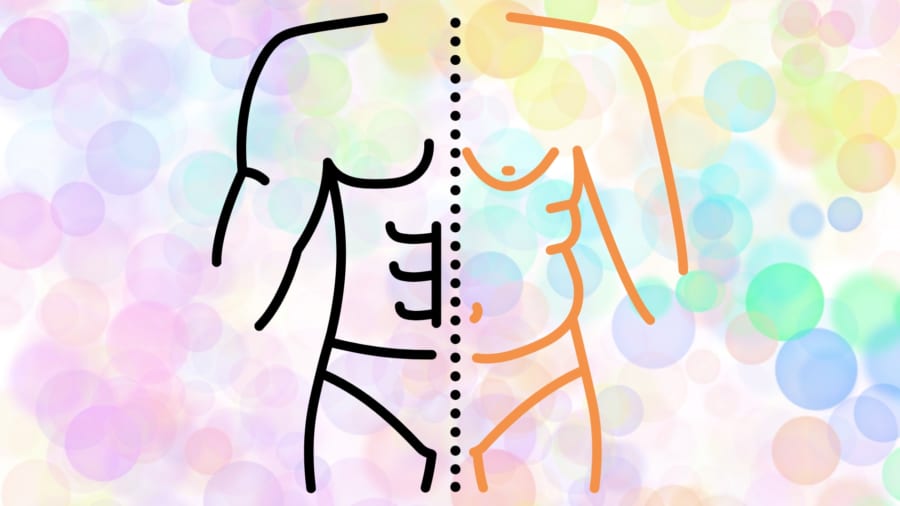
今回の一連の研究は、性別適合手術が決して「心の万能薬」ではない現実を突きつけました。
身体の性を望む姿に近づけることは、性別違和の軽減に役立つ重要なステップです。
それでもなお、長年の心の傷や不安が手術だけですべて癒えるわけではないことがデータから示唆されています。
研究チームも論文中で「性別適合手術はトランスジェンダー当事者のアイデンティティ確認には有益だが、同時に術後のメンタルヘルス問題リスクの増加が見られる。これは術後も継続した配慮ある精神的サポートの必要性を浮き彫りにしている」と強調しています。
言い換えれば、身体的な治療と並行して心のケアを手厚く行う二本立ての支援が欠かせないというメッセージです。
ではなぜ手術を受けた人々の方がメンタルヘルス指標が悪化しているように見えるのでしょうか。
一つ考えられるのは、もともと手術を決断するほど性別違和が強かった人々が多く含まれている可能性です。
専門家は「手術を望むトランスジェンダー当事者は、そうでない人よりも性別不一致の苦痛が大きく、それ自体がうつ病や不安のリスク要因になり得る」と指摘しています。
つまり因果関係が逆である可能性です。
手術によってメンタルヘルスが悪化したのではなく、重い苦悩を抱えていたからこそ手術に踏み切ったという見方で、これは統計上「選択バイアス」と呼ばれる現象です。
しかしリスクが「手術群」で高く観測された理由は、単に「もともと苦悩が深い人ほど手術を選びやすい」という選択バイアスだけでは全てが説明しきれるとは限りません。
たとえば研究者や臨床現場で指摘されている主な要因は以下のように複数重なり合うと考えられます。
まず、外科的侵襲そのものが大きなストレス源になります。
術後の疼痛や合併症、長期にわたる創部管理は睡眠障害や社会生活の制限を招き、気分の落ち込みを誘発しやすいことが知られています。
次に、ホルモン療法の再調整です。性別適合手術後はエストロゲンやテストステロンの用量が変わりやすく、その過程でホルモン濃度が乱高下すれば気分変調や易うつ性を起こしやすくなります。
さらに、手術を経て外見が大きく変化すると、家族や職場・社会からの視線や差別が一段と強まる場合があります。
とくに女性化手術後は声・顔・体形など可視化される部位が多く、“パッシング”できない場面でのストレスが増し、マイクロアグレッション(ささいな差別的言動)の累積がメンタルヘルスを蝕みます。
加えて「これで幸せになれるはず」という高い期待と、現実とのギャップも大きな落胆要因です。術後も心の違和感や社会的障壁が残ったとき、期待外れ感が強いほど抑うつリスクが上がります。
手術費用や休業による経済的負担、保険審査や書類手続きの煩雑さもストレッサーですし、医療機関やカウンセラーが地域に少なくフォローが薄い場合は孤立感が深まることもあります。
こうした外科的・内分泌的・社会心理的・経済的ストレスが複合的に作用し、手術群でうつ病が統計的に有意に高く観測されたと考えられます。
ただ繰り返しますが今回の研究は観察研究であり、介入前後の変化を直接測定したものではないため、「手術そのものが症状を悪化させた」と断定することはできません。
研究チーム自身も、前向きに追跡調査を行ったわけではない点や、社会的支援の有無など測定できなかった要因が結果に影響している可能性を認めています。
しかし一方で、「手術を受ければ心が楽になる」という一般的な期待に反して、受けた人の方が高い割合で苦しんでいる現実は見過ごせません。
マンハッタンの心理療法士は「性別適合手術は外見をアイデンティティに沿ったものに近づける上で極めて重要だ。しかし万能薬では決してない」と語ります。
実際、身体の不一致という「屋根の穴」を塞いでも、周囲の無理解や孤独感という別の雨が降り続けば、再び心に染み込むようなものです。
フロリダの脳神経外科医は「手術を受ければハッピーになれるという保証はどこにもない。
因果関係なのか相関関係なのか、誰にも断言できない」と指摘しています。
大切なのは「手術さえすれば全て解決」という過度な期待を避け、術前術後を通じて当事者を取り巻くサポート体制を強化することです。
研究者らも「偏見や烙印を押されるストレスは、手術の前後を問わずトランスジェンダー当事者のメンタルヘルスに影響し続ける」と指摘し、社会全体で理解と支援を広げる重要性を訴えています。
今回の新知見は一見ショッキングですが、裏を返せば「これまで以上に寄り添う医療が必要だ」というメッセージでもあります。
性別適合手術という大きな決断をした後も、当事者の心には不安や孤独が残っているかもしれません。
だからこそ専門のセラピストによるカウンセリングや、同じ立場の仲間による支え、家族や友人の理解など多角的な支援ネットワークが不可欠です。
近年はトランスジェンダー当事者向けのメンタルヘルス資源も充実しつつあり、相談先や支援団体の情報発信も進んでいます。
こうしたリソースを活用し、「身体のケア」と「心のケア」を両輪に、トランスジェンダー当事者が安心して暮らせる社会を目指すことが求められています。




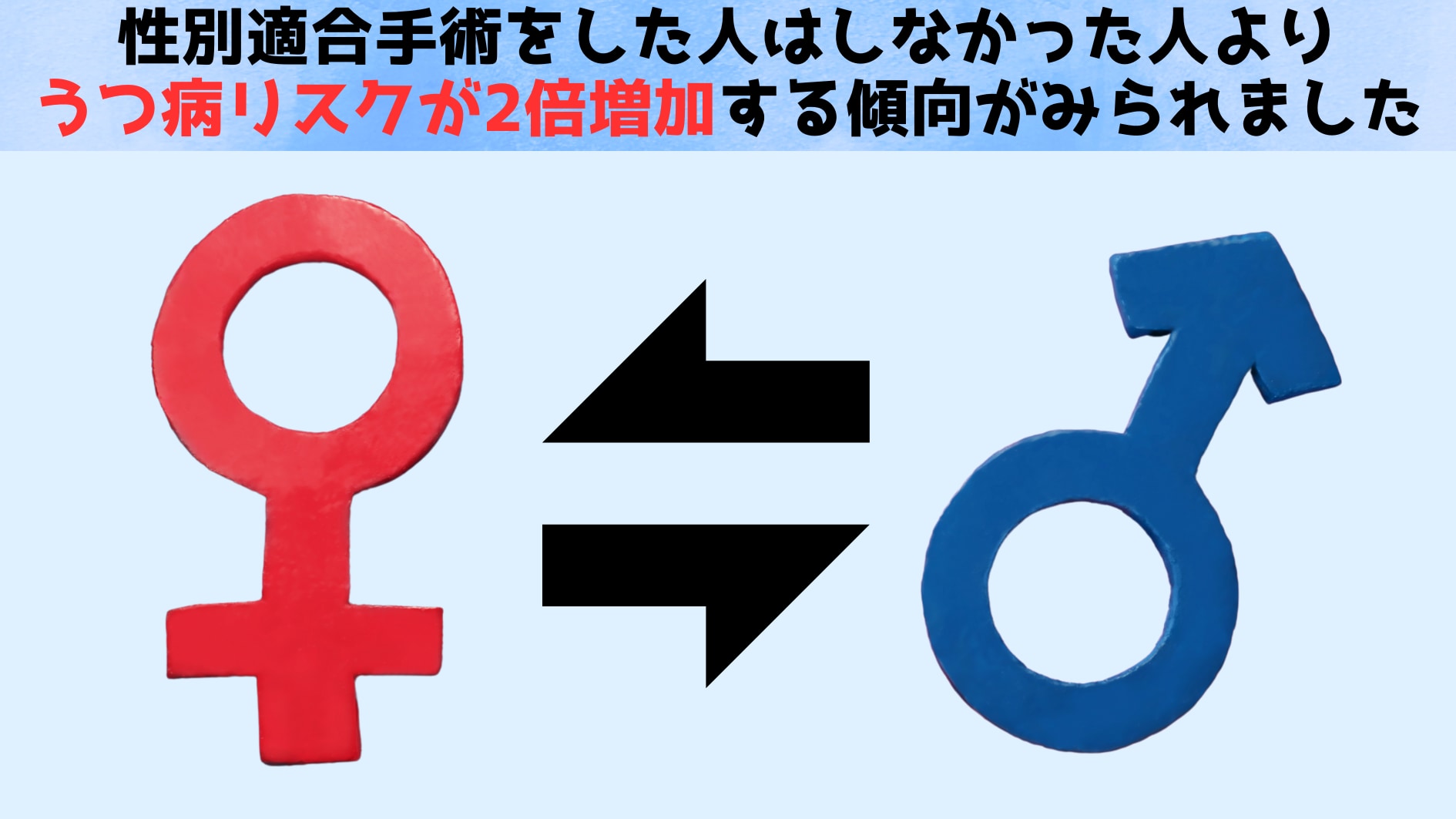









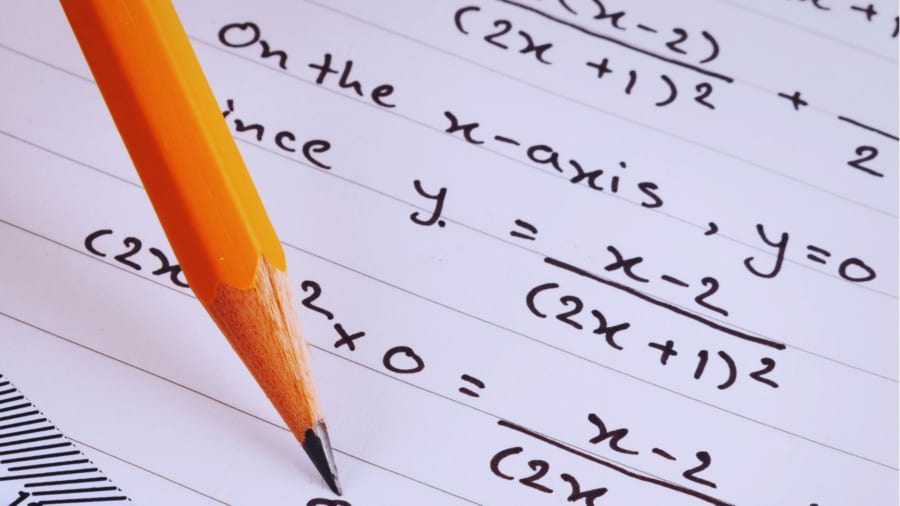














![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




























性別変えたところでその人が理想とする存在になれるわけではないですからね。
その人をベースにした違う性別の存在になるだけなわけですから。ゲームやVR空間の中のアバターとは違いますからね。