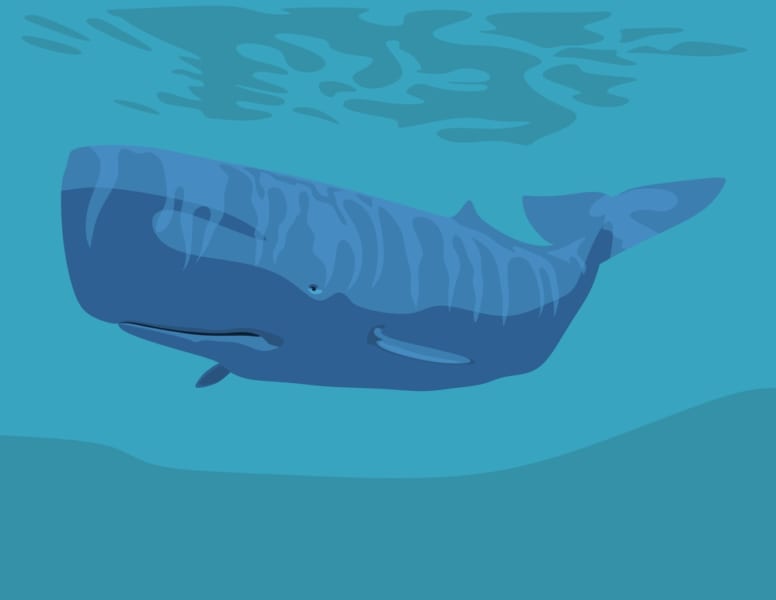全体では増加傾向の牛乳消費

2018年、英Guardian誌に掲載された記事「牛乳に愛想を尽かした私たち」では、人々の関心が植物性の代替ミルクへ移行し、牛乳の人気が落ちていることが報道されました。
ですが、統計では、牛乳の消費量は1998年以降、世界的に年々拡大を続けており、2017年には8億6,400万トンの牛乳が消費されたとのこと。2030年までに、牛乳消費量は35パーセント増え、11億6,800万トンに上ると予測されています。
ところが、各地域に目を向けると、意外な傾向が見えてきます。2010年に米国で行われた食料消費に関する調査では、米国国内の牛乳消費量が、炭酸飲料の人気上昇にともないここ数十年で落ちていることが明らかになったのです。反対に、アジアを含む発展途上国では牛乳の需要が高まったため、世界全体で見た時には消費量が増えているというわけです。
また、187ヶ国の人々を対象とした2015年の調査では、牛乳を飲む習慣は高齢者でよく見られることが示されました。言い換えれば、若年層では牛乳の人気が落ちているということ。とはいえ、少なくとも向こう10年間は、代替ミルクが牛乳に取って代わることは無さそうです。
それにしても、人々の多くがラクターゼ活性維持の特性を持たないアジアで、牛乳の需要がこれほど高まっていることは驚きですね。消化の問題や加工の手間という壁が存在しても、人々が牛乳を飲むことに大きなメリットを感じているということでしょう。
事実、国連食糧農業機関は、発展途上国の人々へ向け、牛乳が入手できない場合や、牛乳の価格が高い場合でも、リャマなどの家畜の乳を摂取するよう推奨しています。
他の動物の乳を、時には加工の手間も惜しまずに摂取し続ける私たち。人間が自然から享受する恩恵は、計り知れません。




















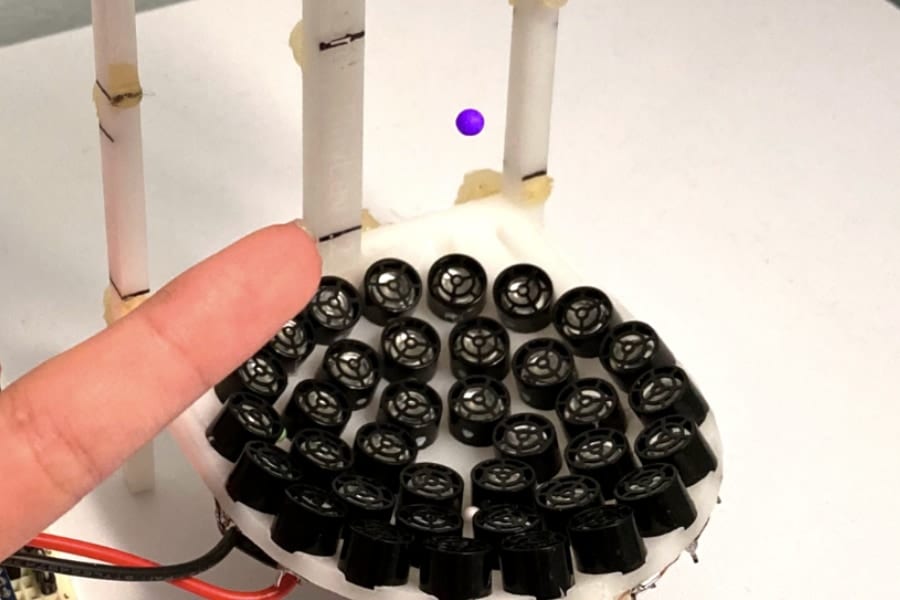









![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)