分岐した運命:クマムシの“超耐久”とオンシフォラの“脆弱”が生まれた理由
クマムシ(緩歩動物)とオンシフォラ(有爪動物)は、パナルトプロダの共通祖先から分かれたきわめて近い存在でありながら、耐久性の面では大きく差があります。
クマムシは乾燥状態で体内水分をほぼ失っても休眠状態(クリプトバイオシス)に入り、さらには宇宙空間に晒されても生還例があるほどの強靱さを獲得しました。
一方、オンシフォラは高い湿度を要し、わずかな乾燥や温度変化にも弱い身体を持っています。
こうしたギャップを生んだ要因の一つは、やはり両者が置かれた環境の違いです。クマムシは苔や地衣類など周期的に水分が失われる環境や、極地・高山といった厳しい条件にも進出し、乾燥や放射線などへの強力な抵抗力を身につけてきました。
一方でオンシフォラは常に湿度の高い森林床を拠点とし、粘着液による捕食という生存戦略を磨く方向へ特化。苛酷な乾燥環境に向き合う必要性が低かったため、耐久性を高める遺伝子やタンパク質を発達させる圧力が小さかったと推測されます。
さらに、クマムシにはDNAを保護するDsupタンパク質のように極限環境への耐性を可能にする分子機構が複数知られていますが、オンシフォラは柔軟な体と“スライムガン”を駆使する狩りの戦略を重視するなど、同じ祖先から分かれたとは思えないほど進化の方向性が異なりました。
まとめると、クマムシが“超耐久”を獲得したのは、過酷なニッチを生き抜くために強い選択圧が働いたからであり、オンシフォラが“脆弱”なまま湿潤環境に適応し続けたのは、乾燥への対応を高めなくても十分に繁栄できたからだと言えそうです。
こうした対照的な進化の姿は、「同じ祖先から分かれた生物が、環境や生態の違いに合わせてどれだけ多様な進化の道を辿るか」を雄弁に物語っています。小型化と極限環境耐性に特化するか、柔軟な体と捕食効率を高めるか――生物進化の多彩さを改めて感じさせる好例でしょう。













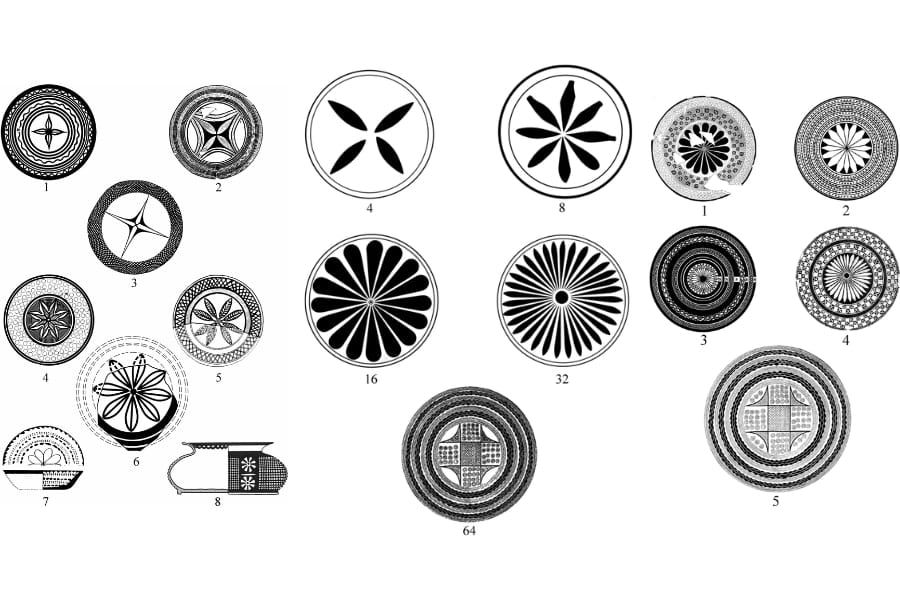


















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




























記事中、パナルトプロダと連呼してるが
パナルトロポダの間違いでしょう
「オンシフォラ」もオニコフォラですよね
カギムシは日本に居ないはずだけど、報告自体はあったの?
クマムシの小形化は食料の乏しさに対する最大の適応でしょうか? また小形化すれば体表面積の割合が高くなり表面からの水分の逃散が致命的となる為に乾燥対策が不可欠だったのでしょう。体積が極端に小さくなると外気温に瞬時になるため位置移動が間に合わないため耐温度性が不可欠だった!